顎の関節に痛みや雑音などが生じる顎関節症は、誰にでも生じ得る病気です。皆さんも口を開けた時にカクンと音が鳴ったり、口の開きにくさを感じたりした経験があるかもしれませんが、その背景には顎関節の異常が潜んでいる可能性も十分にあります。とくに上下の歯列の噛み合わせに問題を抱えている人は要注意です。ここではそんな顎関節症の原因や症状、悪い噛み合わせとの関係などを詳しく解説します。
顎関節症について
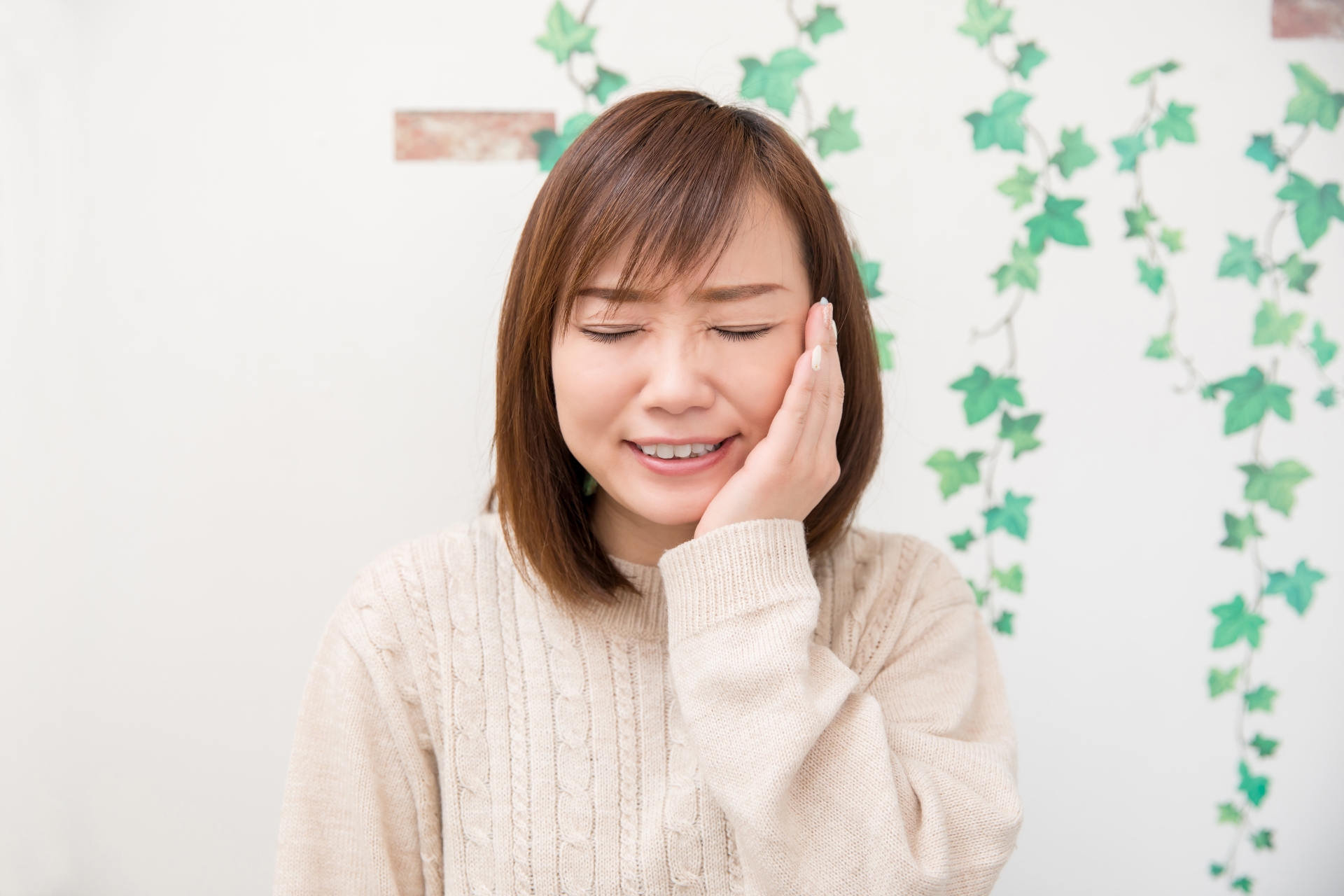 はじめに、顎関節症の基本事項を確認しておきましょう。
はじめに、顎関節症の基本事項を確認しておきましょう。
顎関節症とは
顎関節症とは、顎の関節やその周囲の筋肉に痛みなどの不快症状が現れる病気です。普段生活をしていて気にならない程度の軽症例から、食事や会話に大きな支障をきたす重症例まで、症状の現れ方はさまざまです。年月の経過とともに症状が軽くなっていくケースもあるため、いろいろな面で特殊な病気といえるでしょう。
顎関節症の原因
顎関節症の原因としては、次の5つが挙げられます。
原因1:TCH(歯列接触癖)がある
食事の時以外でも上下の歯列を接触させてしまう習癖です。食べ物を介在させずに歯が直接接触することから、歯はもちろんのこと、歯周組織や顎関節にも多大な負担がかかります。スマホやパソコンの画面をじっと見つめている時に起こりやすい症状で、近年、急速に増えている悪習癖です。
原因2:強いストレスや緊張に晒される
社会生活の中で、強いストレスや緊張に晒される場面は多々あります。そんな時に歯ぎしりや食いしばりをすると、顎関節に大きな力が加わって、顎関節症を誘発することになります。
原因3:顎の負担のかかる悪習慣
歯ぎしりや食いしばり以外にも頬杖をつく癖や片側だけで噛む癖、うつ伏せ寝といった習慣も顎関節に大きな負担がかかることから、顎関節症の発症リスクを高めます。
原因4:転んで顎を強打する
転んだ際に顎を強打すると、その衝撃が顎関節へとつながって痛みや炎症を引き起こします。顎関節を構成する骨や軟組織に不可逆的な異常が生じた場合は、顎関節の機能を障害して、痛みや関節雑音などを引き起こすようになります。
原因5:噛み合わせに異常がある
上下の噛み合わせに異常がある不正咬合(ふせいこうごう)も顎関節症の原因となる場合があります。なぜなら不正咬合では特定の歯に噛んだ時の力が集中するため、咀嚼運動の支点となる顎関節にその影響が及びやすいからです。
顎関節症の症状
顎関節症は、原因がいくつかに分かれるだけでなく、認められる症状にもバリエーションがあります。以下に挙げる症状もケースによって現れるものが異なるため、あくまで参考程度に捉えてください。
- 口を開けると「カクン」「ジャリ」といった雑音が鳴る
- 口を開け閉めすると顎関節やその周囲の筋肉に痛みを感じる
- 食べ物を噛むと顎が痛い
- 口を大きく開くことができない
- 下顎を左右に動かす時に引っ掛かりを感じる
噛み合わせの問題と顎関節症
 ここからは、噛み合わせの問題と顎関節症の関連についての解説です。
ここからは、噛み合わせの問題と顎関節症の関連についての解説です。
噛み合わせの不正が顎関節症に与える影響
下顎骨は、顎関節を介して頭蓋骨にぶら下がるような形で機能しています。そのため、上下の噛み合わせにずれなどの異常があると、下顎骨の位置や動きを不安定化させ、頭蓋骨との連結部分である顎関節に大きな影響をもたらすのです。また、咬筋や側頭筋といった顎関節周囲の筋肉は、そうした不安定な状態で機能することになることから、過剰な緊張を強いられることも珍しくないのです。その結果として、関節円板のずれや骨の異常、筋肉の痛みなどを引き起こします。
噛み合わせの不正を見分けるポイント
噛み合わせの不正は、次の5つのポイントに着目することで見分けることが可能です。
ポイント1:上下の歯列の正中線
上下の歯列の正中を確認し、一致していない場合は不正咬合が疑われます。少なくとも上下どちらかの顎が左か右にずれています。
ポイント2:早期接触が認められる
自然に噛んだ時に、特定の歯だけ先に接触する場合は、噛み合わせに異常があります。早期接触は、特定の歯や歯茎だけでなく、顎関節にも大きな悪影響をもたらします。
ポイント3:噛んだ時の水平的なずれ
奥歯で噛んだ割り箸がガタガタと動揺したり、どちらか一方に傾いていたりする場合は、噛み合わせに異常が認められます。
ポイント4:カチカチした時の接触部位が左右非対称
奥歯でカチカチと噛んだ時に左右で非対称な場合は、噛み合わせがずれています。
ポイント5:誤って頬の内側の粘膜を噛む
口腔粘膜を誤って噛んでしまう行為を「誤咬(ごこう)」といいます。噛み合わせが悪かったり、適合の悪い入れ歯を使っていたりする人に見られやすい症状です。
顎関節症の診断方法
 続いては、顎関節症を診断する方法についてです。ここではセルフチェックする方法と、病院で診断する方法を解説します。
続いては、顎関節症を診断する方法についてです。ここではセルフチェックする方法と、病院で診断する方法を解説します。
自分でできる顎関節症のチェック方法
顎関節症をセルフチェックする場合は、次の方法を実践してみましょう。
方法1:口の開閉時に痛みがある
口を開け閉めした際に、顎関節や顎の周囲の筋肉に痛みがある場合は、顎関節症が疑われます。
方法2:口を大きく開けられない
人差し指・中指・薬指の3本を縦に重ねて口に入れることができない場合は、開口障害が認められます。その原因が顎関節によるものかどうかは、精密検査を行ってみなければわかりません。
方法3:口を開けた時に音が鳴る
口を開けた時に「カクン」「ジャリ」といった雑音が鳴る場合は、関節円板の異常が疑われます。何らかの理由で顎関節に大きな負担がかかり、関節円板が転位している可能性が高いため、専門の医療機関で検査を受けると良いでしょう。
病院での顎関節症の診断の流れ
病院で顎関節症の診断をする場合は、次の流れで検査を行います。
- ステップ1:咀嚼筋や舌骨上筋群の触診
- ステップ2:顎関節の痛みの診査
- ステップ3:開口路と開口量の評価
- ステップ4:画像診断
ステップ4の画像診断では、顎関節まで撮影できるレントゲン「パノラマ」に加えて、軟組織の描出に優れたMRI、骨の状態を把握しやすいCTなどを必要に応じて組み合わせながら進めていきます。とくに顎関節症の診断では、関節円板や関節包靭帯の状態を検査しやすいMRIの重要性が高くなっています。
顎関節症への対処方法
 顎関節症を発症している人は、日常生活で次の点に注意しましょう。
顎関節症を発症している人は、日常生活で次の点に注意しましょう。
できるだけ顎に負担をかけない
顎関節症では、関節を構成する骨や軟組織、その周りの筋肉に大きなダメージを負っているため、それ以上負担をかけないことが大切です。具体的には、下段で説明する点に配慮することで、顎への負担を軽減できます。
両方の歯で噛むようにする
食事をする時は、左右均等に噛むことが大切です。片側だけで噛んだり、前歯だけで咀嚼していたりすると、顎関節症に過剰な負担がかかります。
柔らかいものを食べる
健康な状態であれば、噛み応えのあるものを食べることで、唾液の分泌が促されたり、咀嚼筋が鍛えられたりして良いのですが、顎関節症を発症している場合は、できるだけ柔らかいものを食べるようにしてください。
歯を食いしばらないようにする
食いしばりや歯ぎしりは、顎関節症の症状を悪化させる原因となります。強いストレスがかかったり、物事に集中したりしている時も意識的に食いしばりを避けるよう心がけましょう。
仰向けで寝るようにする
うつ伏せ寝は、顎関節症の主な原因のひとつです。仰向けで寝るようにすることで、顎への負担が減り、顎関節症の症状も緩和されることでしょう。
顎関節症の治療方法
 顎関節症で日常生活に支障をきたすような症状が出ている場合は、歯科医院や病院での治療が必要となります。
顎関節症で日常生活に支障をきたすような症状が出ている場合は、歯科医院や病院での治療が必要となります。
理学療法
理学療法士が主体となって行う治療です。咀嚼筋に電流を流して血流を改善したり、マッサージをしたりすることで、筋肉の緊張やこり、痛みを取り除きます。理学療法を受けた際には、自分で咀嚼筋をマッサージする方法も学んでおくと、セルフケアの幅も広がります。
スプリント療法
プラスチック製のマウスピース(スプリント)を使う治療法です。患者さんの口の状態にカスタマイズしたスプリントを夜間に装着し、下顎を正常な位置へと誘導します。上下の歯列間にスプリントが介在することで、歯と歯が直接、接触するのを防ぐ役割も果たします。スプリントの装着を6〜12ヵ月程度、継続すると下顎も正常な位置に固定化され、顎関節症の原因も根本から取り除くことが可能となります。ただし、患者さんの症状によっては、スプリント療法だけで顎関節症の改善が見込めないこともあります。
薬物療法
顎関節症の原因となっている咀嚼筋の活動を薬物で抑制したり、痛みを服薬でコントロールしたりする方法です。
咬合再建
噛み合わせの異常が顎関節症の原因となっているケースでは、咬合再建が必要となることもあります。咬合再建とは、噛み合わせを作り直す方法で、さまざまな歯科治療を組み合わせることが多いです。例えば、たくさんの歯を失ったことで噛み合わせが不安定になっている場合は、失った歯を補う補綴治療(ほてつちりょう)が必要となります。
入れ歯やブリッジ、インプラントがその代表で、欠損部に人工歯が配置されることで噛み合わせの安定化に大きく寄与します。今現在、装着している詰め物・被せ物・補綴装置に不具合があり、全体の噛み合わせを乱しているのであれば、それらを調整する必要があります。そうした上下の歯列全体の噛み合わせを再建することで、顎関節症を根本から改善できる場合もあるのです。
顎関節症の予防方法
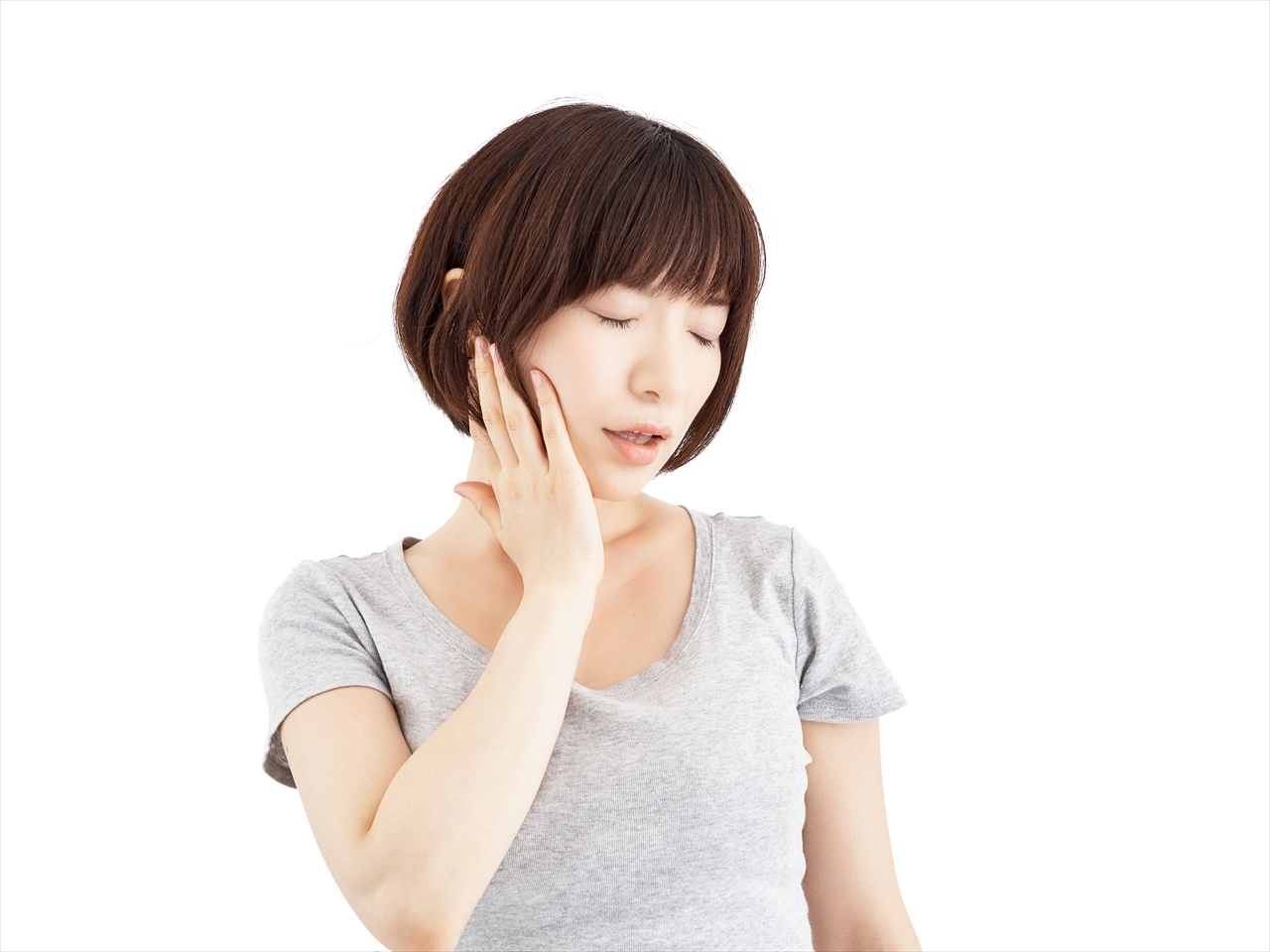 口を開ける時や食べ物を噛む時に痛みを感じる顎関節症は、時に耐えがたいストレスをもたらすこともあります。それだけに顎関節症はできる限り予防したいものです。まだ、顎関節症の症状が認められない人や顎関節を徹底的に予防したいという人は、次の3つの方法を実践すると良いでしょう。
口を開ける時や食べ物を噛む時に痛みを感じる顎関節症は、時に耐えがたいストレスをもたらすこともあります。それだけに顎関節症はできる限り予防したいものです。まだ、顎関節症の症状が認められない人や顎関節を徹底的に予防したいという人は、次の3つの方法を実践すると良いでしょう。
悪癖の改善
顎関節の原因となる歯ぎしり・食いしばり、片側だけで噛む癖、うつ伏せ寝、頬杖をつく癖などは、今日からでも改善するよう努めましょう。こうした悪癖は、無意識に行ってしまうことの方が多いですが、周りの人に指摘されたり、自覚したりした際には、意識的に改善するようにしてください。とりわけ歯ぎしり・食いしばりは、顎関節症だけでなく、歯の摩耗や破折、歯茎の炎症などをもたらすことがあるため、除去するに越したことはありません。
ストレスの緩和
ストレスも顎関節の主な原因のひとつです。現代社会で生活している以上、ストレスから完全に逃れることはできませんが、ストレスを受ける機会を減らしたり、受けたストレスを自分なりの方法で緩和したりすることは可能です。例えば、週末は必ず自分の趣味の時間を作ることで、ストレスを発散しやすくなります。定期的にウォーキングやランニングなどの運動をすることでもストレスの緩和につながることでしょう。 ストレスの有無や量は可視化することもできなければ、自覚することさえ難しい場合もあります。そんな時は、歯ぎしりや食いしばり、TCH(歯列接触癖)といった悪習癖が生じていないかセルフチェックすると良いでしょう。そうした悪習癖は、顎関節症のリスク因子となるだけでなく、強いストレスや緊張に晒されているかの指標にもなります。ちなみに、歯ぎしりの症状が強い人は歯が摩耗していくため、定期的な歯科検診を受けていればその習癖を指摘してもらえることが多いです。
顎関節のストレッチ
顎関節やその周りの筋肉のコンディションを良好に維持することでも顎関節症は予防しやすくなります。ですから、普段から顎関節を正常に動かすストレスを行ったり、咬筋や側頭筋をやさしくマッサージしたりすることは顎関節症予防として推奨できます。ただし、誤った方法でストレッチやマッサージをすると、かえって顎関節症のリスクを上昇させることもあるため、正しい方法は歯科医師や理学療法士といった専門家から学んだ方が良いです。歯科医院であれば、定期検診・メンテナンスを受けた際に、顎関節症予防に有効なストレッチやマッサージの方法を指導してもらえることがあります。
編集部まとめ
 今回は、顎関節症と噛み合わせの関係について解説しました。上下の噛み合わせの異常は、咀嚼運動の支点となる顎関節に大きな負担をかけることから、顎関節症の原因となり得ます。それだけに噛み合わせに異常がある場合は、早い段階で歯科での治療を受けておいた方が良いといえるでしょう。本文でも説明したように、悪い噛み合わせである不正咬合は、自宅で簡単にチェックする方法がありますので、該当する症状が認められる場合は、専門家による診査・診断を受けるようにしましょう。また、顎関節症の原因は噛み合わせの異常だけではないため、顎関節やその周囲の筋肉に痛みがあったり、口を開けた時にカクンと音が鳴ったりする場合も一度、歯科や口腔外科、整形外科などで診察を受けた方が良いといえます。
今回は、顎関節症と噛み合わせの関係について解説しました。上下の噛み合わせの異常は、咀嚼運動の支点となる顎関節に大きな負担をかけることから、顎関節症の原因となり得ます。それだけに噛み合わせに異常がある場合は、早い段階で歯科での治療を受けておいた方が良いといえるでしょう。本文でも説明したように、悪い噛み合わせである不正咬合は、自宅で簡単にチェックする方法がありますので、該当する症状が認められる場合は、専門家による診査・診断を受けるようにしましょう。また、顎関節症の原因は噛み合わせの異常だけではないため、顎関節やその周囲の筋肉に痛みがあったり、口を開けた時にカクンと音が鳴ったりする場合も一度、歯科や口腔外科、整形外科などで診察を受けた方が良いといえます。
参考文献
