「親知らずの抜歯で、もしかしたら歯を砕く必要があるかもしれません」と歯科医師に言われたら、不安に感じる方は多いでしょう。
抜歯でも怖いのに砕くと聞くと、どのような治療なのか、痛みはどのくらいなのかと心配になるのは当然です。
斜めや横向きに生えている歯をそのまま抜くと負担が大きいため、親知らずを砕くことで、歯を小さく分けて取り出すことができ、痛みや腫れをできるだけ抑えることができます。
この記事では、親知らずの基本的な知識から、なぜ砕いて抜歯する必要があるのか、具体的な方法、抜歯後の過ごし方まで、わかりやすく解説します。
親知らずの基礎知識

親知らずの抜歯を正しく理解するためには、まず親知らずがどのような歯なのか、そしてどのように生えてくるのかなど、基本的な知識から見ていきましょう。
以下では、親知らずの定義と、多様な生え方を解説します。
親知らずとは
親知らずとは、前歯から数えて8番目に位置し、上下左右の一番奥に生えてくる永久歯です。
多くの場合、ほかの永久歯がすべて生えそろった後に出てくるため、生えるための十分なスペースがない場合があります。
スペースが不足していると、後述するような横向きの生え方になったり、歯茎に埋まったままになったりする原因となりかねません。
すべての方が4本の親知らずが出るわけではなく、生まれつき親知らずがない方や、骨の中に埋まったまま生えてこない方もいます。
親知らずの生え方
親知らずの生え方は、顎のスペースや向きによって人それぞれ異なり、主に3つのタイプに分けられます。この生え方の違いが、抜歯の難易度や方法に大きく関わってきます。
まっすぐ生えている
親知らずがほかの奥歯と同じように、まっすぐ正常な向きに生えているケースです。
十分なスペースがあり、きれいに生えそろっていれば、歯みがきもしやすく、特に問題を起こさないこともあります。
抜歯の難易度は高くなく、ほかの歯を抜くのと同じような単純抜歯で済むことがほとんどです。
ただし、歯がまっすぐ生えていても、歯みがきしにくくむし歯になっていたり、一部しか出ておらず炎症をくり返したりする場合は、抜歯が必要な場合があります。
横向きや逆向きに生えている
顎のスペースが足りない場合、親知らずが真横を向いて、手前の歯(第二大臼歯)の根元を押すように生えてくる場合があり、水平埋伏と呼びます。
水平埋伏は、手前の歯をむし歯にしたり、歯並び全体を乱したりする原因となるため、抜歯が推奨されるケースが多いです。
抜歯の際にはそのままでは取り出せないため、歯茎を切開し、歯をいくつかに砕いて取り出す分割抜歯が一般的な方法です。
歯茎に埋まっている
親知らずが歯茎や顎の骨の中に完全に埋まったままで、外からは見えない状態を完全埋伏と呼びます。
また、頭の一部だけが歯茎から出ている状態は半埋伏といいます。
埋まっている親知らず(埋伏歯)は、特に半埋伏の場合、歯と歯茎の間に汚れが溜まりやすく、強い炎症(智歯周囲炎)を引き起こす原因になりやすいです。
抜歯する際は、歯茎を切開し、場合によっては歯を覆っている骨を削ってから、歯を分割して取り出す必要があります。
親知らずは必ず抜歯しなければならない?

親知らずは抜くものと思うかもしれませんが、すべての親知らずを抜歯する必要はありません。
抜歯すべきかどうかは、親知らずの生え方や周囲の歯、そしてお口全体の健康状態によって総合的に判断されます。
親知らずを抜かなくてもよいケース
親知らずを抜かずに残せるのは、いくつかの条件を満たしている場合です。
- まっすぐに生えていて、上下の歯が正常に噛み合っており、奥歯としての機能を果たしている場合
- 歯みがきが問題なくできており、むし歯や歯周病になっていない
将来的に、手前の奥歯を失った際に、ブリッジの土台や移植する歯として親知らずを利用できる可能性もあるため、健康な状態であれば無理に抜かない選択肢もあります。
親知らずの抜歯が必要なケース
一方で、以下のようなケースでは、将来的なトラブルを防ぐために抜歯が推奨されます。
- 智歯周囲炎を繰り返す:親知らずの周りの歯茎が腫れたり痛んだりする炎症をくり返している場合。
- 痛みや腫れがある:親知らず自体がむし歯になって痛む、または歯茎の炎症がひどく腫れている場合。
- 歯並びに影響を与える:親知らずが手前の歯を押し、歯並びを乱す原因となっている、または可能性がある場合。
- 手前の歯がむし歯になるリスク:親知らずとの間に汚れが溜まりやすく、隣接する健康な歯がむし歯になる可能性が高い場合。
- 口臭の原因になる:清掃が不十分で汚れが溜まり、口臭の原因となっている場合
- 噛み合わせの問題:上下片方しか生えておらず、噛み合う相手の歯茎を傷つけたり、顎関節症の原因になったりする場合。
上記のような症状がある場合は、放置するとより大きな問題につながる恐れがあります。歯科医師と相談のうえ、適切な時期の抜歯が望ましいです。
親知らずを抜歯するメリット・デメリット

親知らずの抜歯を検討する際には、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが、納得のいく決断を下すために不可欠です。抜歯によって得られるメリットと、伴う可能性のあるリスクなどを解説します。
親知らずを抜歯するメリット
親知らずを抜歯するメリットは、現在起きている問題や将来起こりうるリスクを根本的に解決できることです。
例えば、繰り返し起きている智歯周囲炎の痛みや腫れを治療できます。
また、親知らずが原因で清掃が難しかった部分がなくなり、手前の大切な歯をむし歯や歯周病から守ることにもつながります。
さらに、女性の場合は、妊娠中のホルモンバランスの変化で親知らずが急に痛み出すケースが珍しくありません。
妊娠中は治療が制限されます。妊娠前に親知らずを抜歯しておくと、安心して妊娠や出産期を迎えられるメリットもあります。
親知らずを抜歯するデメリット
親知らずの抜歯は、外科的な処置だからこそデメリットやリスクも存在します。
特に下の親知らずの抜歯で注意が必要なのが、神経への影響です。
歯の根の近くには、下唇や顎の皮膚の感覚を司る神経(下歯槽神経)が通る管があります。
親知らずの根が下歯槽神経に近い場合、抜歯の際に神経が圧迫されたり傷ついたりして、術後に唇や顎に痺れが残るケースがまれにあります。
また、抜歯後には痛みや腫れが伴うことが一般的です。
特に、骨を削ったり歯を分割したりした難しい抜歯ほど、痛みや腫れは強くなる傾向があります。痛みや腫れのピークは術後2〜3日で、通常は1週間ほどで落ち着きます。
親知らずの主な抜歯方法

親知らずの抜歯方法は、歯の生え方によって大きく異なります。
以下では、代表的な2つの方法を見ていきましょう。
ヘーベルを使用する方法
親知らずがまっすぐに生えており、歯の頭がしっかりと見えている場合の抜歯は単純抜歯と呼ばれ、ほかの歯を抜く際と同様の手順で行われます。
この方法は、まず麻酔を効かせた後、ヘーベルという器具を使って歯と骨の間の組織(歯根膜)を剥がし、歯を少しずつ揺らして脱臼させる方法です。
歯が十分に緩んだら、抜歯鉗子というペンチのような器具で歯をつかみ、抜き取ります。
難易度が低い処置であり、短時間で終わる場合が多いです。
ただし、歯の根が曲がっているなど複雑な場合は、後述する分割抜歯が選択されることもあります。
歯肉を切開して除去する方法
親知らずが横向きに生えていたり、歯茎に埋まっていたりする埋伏歯の場合は、単純抜歯では対応できません。
この場合、埋伏智歯抜歯という外科的な処置が必要です。
まず局所麻酔の後、歯茎をメスで切開して剥がし、親知らずを露出させます。
歯が骨に埋まっている場合は、ドリルのような器具で歯を覆っている骨を削るケースも珍しくありません。
歯全体が見えたら、歯を取り出しやすいようにいくつかに分割し、取り除きます。
最後に、切開した歯茎を元の位置に戻し、糸で縫い合わせて終了です。
親知らずを砕く抜歯方法とは?

親知らずを砕く抜歯方法は分割抜歯と呼ばれる、抜歯後の順調な回復を目的とした、計画的な外科手技です。
どのような場合に分割抜歯が必要になるのか、具体的な治療を解説します。
親知らずを砕いて抜歯する必要があるケース
分割抜歯が必要となるのは、主に親知らずをそのままの形で抜歯するのが困難な場合です。
- 横向きや斜めに生えている親知らず
- 部分的に埋没している親知らず
- 歯根が複数に分岐や湾曲している親知らず
親知らずを砕いて抜歯する方法
分割抜歯は、精密な計画のもとで行われます。横向きに埋まっている下顎の親知らずを砕いて抜歯する手順は以下のとおりです。
- 局所麻酔で歯と周囲の感覚を麻痺させる
- 歯茎を切開して、骨から歯を剥がす
- 必要に応じて骨を少し削り、歯を見えるようにする
- 歯を歯冠(上)と歯根(下)に分けて切る
- まず歯冠を取り除き、スペースを作る
- 残った歯根を必要に応じて分けながら取り除く
- 歯茎を縫って、止血を確認して終了
親知らずを砕いて抜歯する際の痛み
抜歯中は局所麻酔がしっかりと効いているため、痛みを感じることは少ないです。
歯科医師は麻酔が効いていることを確認しながら処置を進めるため、もし途中で痛みを感じるようなことがあれば、すぐに対応してもらえます。
術後の痛みは、麻酔が切れる頃から出てきます。麻酔が切れる前に鎮痛剤を服用しておけば、痛みのピークの緩和が可能です。
親知らずを砕いて抜歯した後の過ごし方
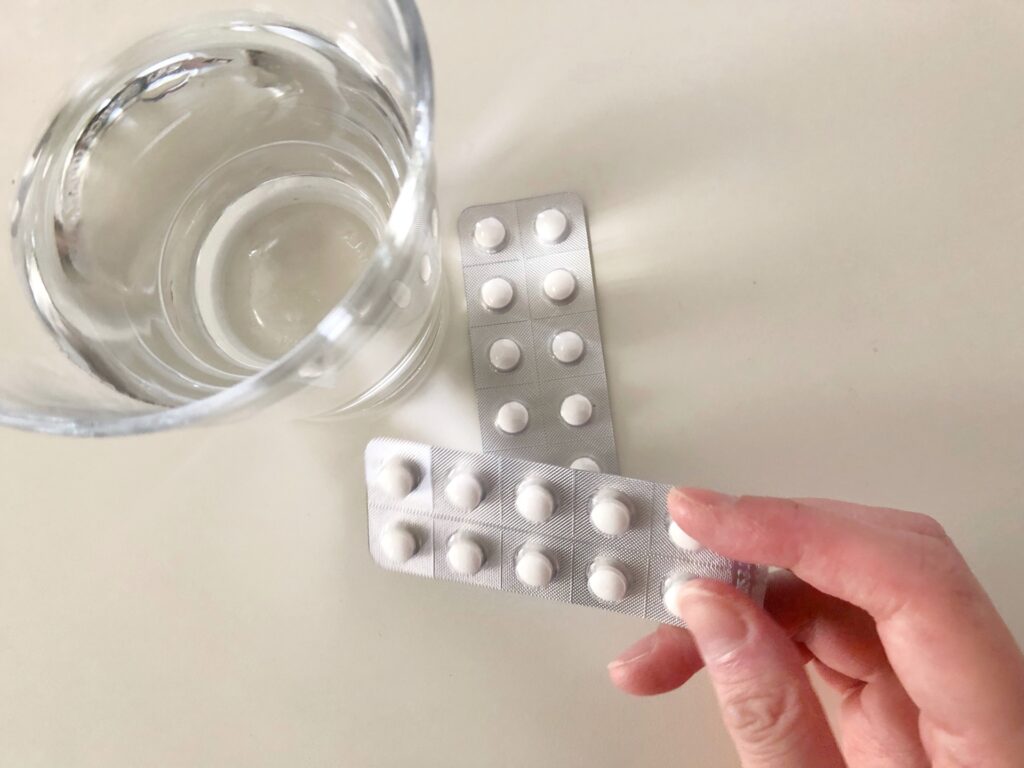
分割抜歯のような外科処置の後は、順調な回復のために術後の過ごし方が重要です。
抜歯後に出る可能性のある症状を理解し、適切なケアを心がけることで、痛みや腫れを少なく抑えられます。
抜歯後に出る可能性がある症状
抜歯後は、個人差はありますが、痛み、腫れ、出血などが起こりえます。痛みと腫れのピークは、一般的に抜歯後から2〜3日後とされています。
痛みに対しては処方された鎮痛剤を服用し、腫れに対しては濡れタオルなどで冷やすと症状が和らぎやすいです。
また、抜歯当日は血がにじむことがありますが、強くうがいをすると固まりかけた血の塊が剥がれてしまい、治りが悪くなる原因になります。
うがいは軽く行う程度にし、激しい運動や長時間の入浴、飲酒など血行が良くなることは避けましょう。
抜歯後の過ごし方のポイント
抜歯後の回復をスムーズにするためのポイントは、薬の管理と日常生活の制限です。
処方された抗菌薬は、感染予防のために指示どおりに飲み切りましょう。
鎮痛剤は、痛みが強くなる前に服用するのが効果的です。麻酔が効いている間に1回目の薬を飲んでおくと、痛みをほとんど感じずに済む場合もあります。
食事は、麻酔が切れてから、抜歯した側とは反対側で、硬いものや刺激物を避けて摂るようにしましょう。また、傷口を指や舌で触らないことも大切です。
症状が強く出る場合は歯科医院で相談を
通常、痛みは数日から1週間で落ち着きます。
ただし、抜歯して2〜3日経ってから、ズキズキとした我慢できないほどの強い痛みが出てきた場合は、ドライソケットという状態になっている場合があります。
ドライソケットは抜歯した穴を覆う血の塊が剥がれてしまい、骨が直接お口の中に露出して感染を起こした状態です。
ドライソケットになった場合、歯科医院での洗浄や投薬などの処置が必要になります。
痛みが日に日に強くなる、顎や耳の方まで響くような痛みがある場合は、我慢せずにすぐに抜歯した歯科医院に相談しましょう。
まとめ

親知らずを砕くと聞くと、「痛そう」と思うかもしれません。。
しかし、実際は無理な力をかけず、身体へのダメージを少なくする、患者さんのための精密な治療法です。
親知らずの抜歯が必要かどうか、どう抜歯するかは、生え方によって決まります。
まっすぐ生えて問題を起こしていなければ抜歯する必要はなく、抜歯する場合でも、すべてのケースで歯を分割するわけではありません。
ご自身の親知らずの状態を歯科医師に正確に診断してもらい、わからないことや不安なことは直接相談して、納得したうえで治療に臨みましょう。
参考文献
