顎関節症が辛くて治療を受けようか考えている方のなかには、治療を受けたら何日で治るかなどが気になるという方もいるのではないでしょうか。治療を始めたけれどあまり変化を実感できず、何日で治るのかと不安になっている方もいるかもしれません。
この記事においては、顎関節症がそもそもどのような症状であるのかをはじめ、顎関節症の原因や治療法、治療を受けたら何日で治るのかなどを解説していきます。
顎関節症でお悩みの方や、治療内容に不安がある方は参考にしてみてください。
顎関節症の基礎知識
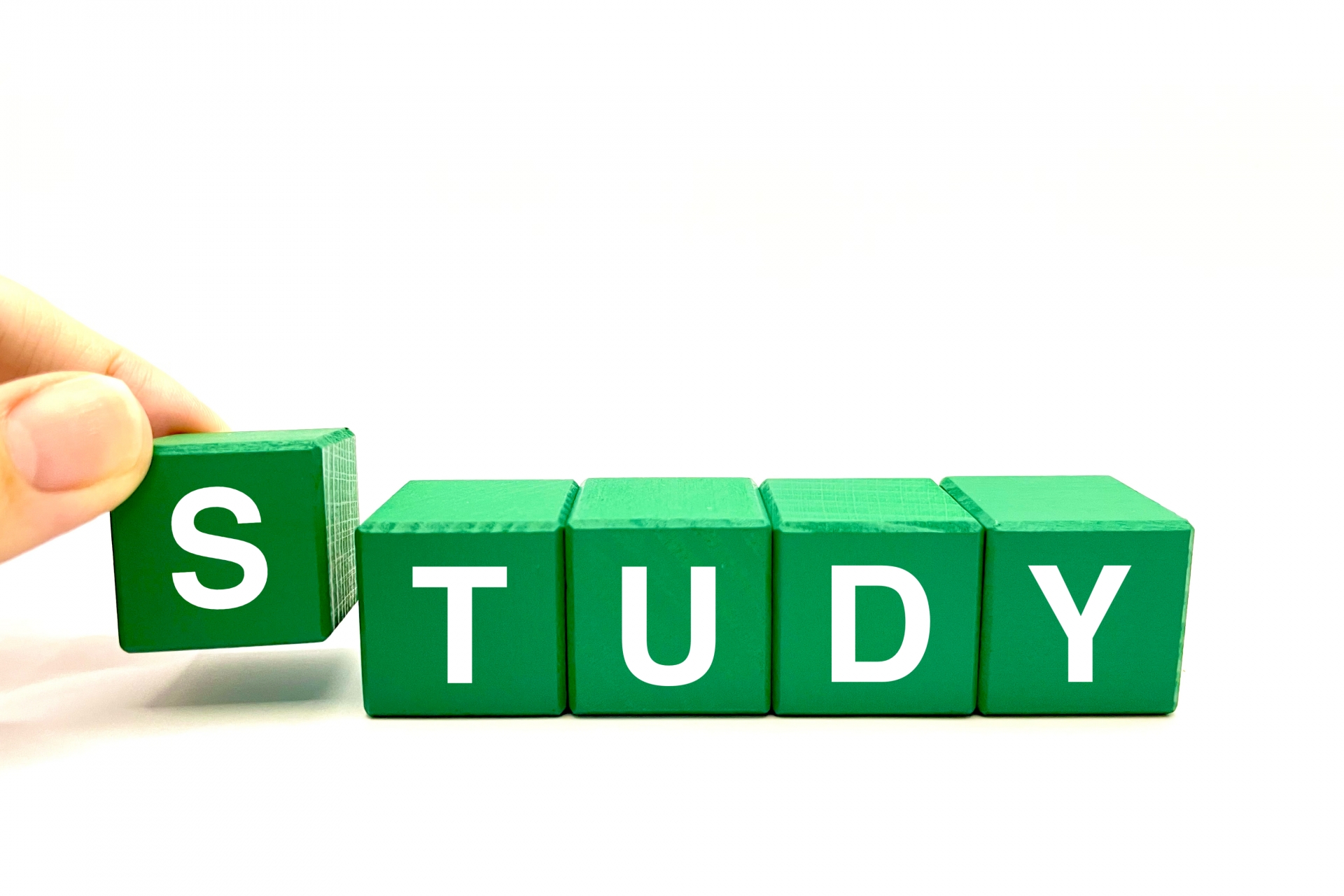
顎関節症という言葉を聞いたことはあるけれど、どのような症状なのかについて詳しくは知らないという方も多いかもしれません。まずは顎関節症がどのようなものなのか、原因なども含めて解説します。
顎関節症とは
顎関節症とは、顎にある関節や、顎の筋肉などに何かしらのトラブルが生じ、痛みや動かしにくさ、動かした際にカクカクという音などが出るといった症状が現れる病気です。上記のいずれかの症状を認め、他の疾患を否定できた場合、顎関節症と診断が行われます。 日常生活に支障がない程度の症状から、食事や会話などが行いにくくなるといった生活上のトラブルにつながる症状まで幅があり、放置していると症状が悪化する場合もあります。
顎関節症は二人に一人は一生のうちに経験するともいわれ、それだけにお悩みの方が多い症状であるといえます。
顎関節症の症状
顎関節症の症状として特徴的なものが関節雑音と呼ばれるもので、これはお口を開いた際にカクカクやミシミシといったような音が聞こえるというものです。
関節雑音がする原因は、顎の関節を動かす際にクッションの役割を果たす関節円板という組織の位置にズレが生じているためで、音がなる仕組みは首や肩を回したときに音が鳴るものと同じです。この音が生じている方は人口の20%近くにのぼると推定されています。
顎関節症の場合、関節が耳の付近にあるため音が気になりやすいですが、音が鳴っているだけであれば治療の必要はないとされ、医療機関にいっても経過観察となる可能性があります。 治療が必要となるのは、顎を動かした際に痛みが出たり、お口を開けにくいと感じたりするような症状がある場合で、関節円板の位置のほか、筋肉の炎症なども影響して生じます。
痛みについてはお口周りだけではなく、こめかみあたりの筋肉に痛みが出るという場合もあり、慢性的な頭痛の原因などになることもあります。
また、お口の開きにくさについては、食事をしっかりと行うことができなくなるケースもあり、結果として全身の不調につながってしまう可能性もあります。 音だけではなく、治療が必要な程度の痛みやお口の開けにくさが生じる割合は、顎関節症を自覚している人の5%ほどと推定されています。
顎関節症のタイプ
顎関節症は、発生している症状やその原因によって1型から5型という5つのタイプに分類されています。 1型は咀嚼筋痛障害と呼ばれるもので、顎の筋肉の炎症などによって、お口を動かした際に顎周辺やこめかみなどに痛みがでるという状態です。顎の筋肉は頭や首、肩にもつながっているため、肩こりや頭痛などを伴うこともあります。 2型は顎関節痛障害と呼ばれるもので、顎の関節にトラブルが生じているものです。開口時や咀嚼時に痛みを感じやすくなります。 3型は関節円板障害と呼ばれ、顎関節のクッションとして働いている関節円板が正常な位置からずれて、関節雑音やお口の開きにくさが生じるものです。
関節円板がずれたり元の位置に戻ったりして関節雑音がなる3a型(復位型)と、関節円板が元の位置に戻らないため、お口を開けにくくなる3b型(非復位型)があります。 4型は変形性顎関節症による症状で、顎の骨が変形してしまうことで痛みや開口障害が現れるものです。骨の変形を伴うため、手術などの治療が必要になることもあります。 そして、上記のどれにも当てはまらないものが5型です。5型は心理的な要因などが関係しているケースもあります。
顎関節症の原因
顎関節症の直接的な原因は関節円板のズレや筋肉の炎症などですが、こうしたトラブルは下記のような原因によって生じる可能性があります。
食いしばりや歯ぎしり
食いしばりや歯ぎしりのような、無意識のうちに歯を強く噛みしめてしまうような癖は、顎関節症を引き起こす要因の一つです。
噛むという行為はとても強い力を発揮する行為ですが、特に食事の際に硬いものを砕いたり、食べ物を磨り潰したりする奥歯では、自分の体重に匹敵するくらいの力がかかるとされています。
食いしばりや歯ぎしりによって、こうした強い力が食事以外のタイミングでも無意識のうちにかかってしまうと、顎周囲の関節や筋肉に強い負担がかかり、顎関節症を引き起こす要因となります。
食いしばりや歯ぎしりは日常的なストレスが原因で生じやすいため、慢性的なストレスにさらされている方は顎関節症なども引き起こされやすいといえます。
歯並び
歯並びの悪さも、顎関節症の要因の一つです。歯並びに問題があり噛み合わせが適切でない場合、食事の際などに通常とは異なるような顎の動かし方が必要となるなどして、顎の関節や筋肉に負担がかかり、顎関節症を引き起こす可能性があります。 なお、以前は歯並びや噛み合わせの問題が顎関節症の主な要因と考えられ、顎関節症を改善するためには歯列矯正などによる治療が重要とされていました。
現在は顎関節症は歯並びや噛み合わせを含め、さまざまな要因が影響して生じると考えられ、治療の際は患者さんそれぞれの症状などにしっかりと合わせることが重要とされています。
うつ伏せ寝や食生活など生活習慣
日常生活のなかにおけるさまざまな癖や、食事内容も顎関節症を引き起こす要因となります。具体的には、下記のような内容に該当する場合は顎関節症のリスクが高まります。
- うつ伏せ寝をよくする
- 頬杖をつく癖がある
- 猫背など姿勢の悪さがある
- 爪を噛むくせがある
- 硬いものをよく食べる
- 片方の歯でばかり噛んでしまいやすい
- 上下の歯が常に接触している(TCH)
うつ伏せ寝や頬杖、爪を噛むといった癖は、顎周囲に負担をかけやすいため、顎関節症の要因となります。また、硬いものを好んで食べる方も、顎に負担がかかりやすいため症状が引き起こされやすいといえるでしょう。 また、安静時にも常に上下の歯が接触した状態になっている、TCHと呼ばれる癖も、顎の筋肉に負担をかける要因の一つです。
上下の歯は安静時には少し隙間が空いている状態が正しい位置なのですが、慢性的な緊張や姿勢の悪さなどがあると常に歯が接触した状態となり、顎の筋肉がリラックスできない状態が持続します。そのため、TCHがある方は日常的に顎の関節や筋肉に負担がかかり続け、顎関節症になりやすいといえます。
外傷など外部からのダメージ
上記のほか、外部からの衝撃による怪我や捻挫なども顎関節症の要因になります。
顎関節症は何日で治る?

口を動かすという日常的な行為で痛みなどが生じる顎関節症は、なるべく早く治したいと考える方も多いと思います。実際に治療を行った場合は何日で治る可能性があるのか、そもそも放置しておいても治ることがあるのかなどを解説します。
顎関節症の一般的な治療期間
顎関節症は、そもそも痛みなどの自覚症状の程度によって診断されるものであり、明確に完治したといえるタイミングの判断が難しい症状です。
そのため、何日で治るかという疑問にはっきりとした答えは出しにくいのですが、セルフケアも含めてしっかりと治療に取り組めば、9割の人は数ヶ月から半年ほどで治すことができると言われています。 また、主な症状が痛みなどである場合は、処方される鎮痛剤などを服用することで素早く症状を改善できる可能性もあります。 そのほか、顎の骨の変形など明確な原因がある場合は手術などを含む外科的治療で改善が可能なため、必要な治療を受けることができる日程や、術後の回復期間を考えれば何日で治るかを推測できるといえます。
顎関節症は自然に治る?
顎関節症のタイプによっては、特別な治療を行わなくても自然に治る可能性があります。
例えば一時的なストレスによって食いしばりなどの癖が生じ、それが原因で筋肉の痛みなどが引き起こされている場合、食いしばりなどの癖が改善されて筋肉の状態が回復すれば、顎関節症の症状も自然と解消します。
顎に何かしらの違和感がある方のうち、7割ほどが1年以内に症状が改善したというデータもあるため、日常生活に大きな影響などがない状態であればしばらく様子をみても問題ないといえるでしょう。
ただし、時間経過に伴い症状が悪化するようなケースでは、やはりなるべく早めに適切なケアを行うことが大切ですので、歯科医院に相談してみるとよいでしょう。
顎関節症の治療法

顎関節症の治療は、症状が引き起こされている原因に合わせて、さまざまな方法で行われます。
痛みなどに対する対症療法
顎周辺の痛みをはじめ、頭痛や肩こりといった症状が出ている場合は、鎮痛剤などを処方して、対症療法でお悩みの改善を目指します。
場合によっては局所麻酔を使用した神経ブロックなども行われます。
マウスピースによる治療(スプリント療法)
スプリント療法は、一人ひとりの歯並びや筋肉の使い方に合わせて作られた専用のマウスピースを寝ている間に装着し、筋肉の使い方などを改善する治療法です。
スプリント療法によって顎関節症を引き起こしているような顎の使い方を修正し、顎の関節や筋肉を休ませることができるようにすることで治療を行います。
マウスピースは寝ている間に装着するだけなので日常生活に影響が少なく、取り組みやすい治療法といえます。 なお、寝ている間に装着するマウスピースとしては、ナイトガードと呼ばれるものもあります。ナイトガードは歯ぎしりなどによる歯への負担を軽減するためのマウスピースで、使用により歯の摩耗などを防ぐためのものです。
ナイトガードは市販されているものもありますが、顎関節症を改善するためには患者さん一人ひとりに合わせて作る専用のスプリントが必要になりますので、顎関節症に対する治療目的であれば歯科医院に相談しましょう。
生活指導によるケア
顎関節症は、TCHや頬杖などの日常的な癖による影響によって生じやすい症状です。歯科医院においては、こうした日常的な癖を問診などで整理し、どのような行為に注意するべきかなどの生活指導によって、顎関節症の改善を目指していきます。
運動療法
お口周りの筋肉の使い方などを改善するために行われる動かし方の指導や、筋肉の緊張をほぐすためのストレッチ方法の指導など、運動療法も顎関節症をケアする治療法の一つです。
理学療法
顎周辺の筋肉をほぐすため、手技によるマッサージや電流によるケア、温熱ケアなどを行うものが理学療法です。
関節周辺の負担を軽減することで、痛みの改善や可動域の増加を目指します。
歯列矯正
歯並びや噛み合わせの悪さが顎関節症の要因になっている場合、歯列矯正が推奨される場合もあります。
歯列矯正はワイヤーや専用のマウスピース型矯正装置を使用して歯に一定の力を加え続け、歯の位置を理想的な状態に整える治療です。
歯列矯正は、ゆっくりと時間をかけて歯を動かしていく治療であるため、治療が完了するまでには1~2年が必要となるケースもあります。
手術治療
顎の骨の変形などが原因の顎関節症であれば、手術治療も検討されます。手術によって顎の可動域を広げることで顎関節症が改善できるため、何日で治るかを推測しやすい治療法であるといえます。
顎関節症のセルフケア方法

顎関節症を改善するためには、適切なセルフケアに取り組むことが大切です。
まずは、上述のような顎関節症の原因となっている癖や生活習慣を見直し、顎に負担をかけないような生活を心がけましょう。
そのうえで、顎周辺を温めたり、適度なマッサージやストレッチを取り入れ、筋肉の緊張をほぐすようにして過ごすと、少しずつ症状を改善していく効果が期待できます。
何日で治るかというはっきりとした基準はありませんが、継続して取り組むことで少しずつお悩みを軽減していくことができるでしょう。
マッサージやストレッチの方法は歯科医院で指導を受けることができますので、症状が気になっているかたは一度顎関節症の診療に対応している歯科医院に相談してみてはいかがでしょうか。
顎関節症の予防方法

顎関節症を予防するためには、やはり原因となる生活習慣や癖に注意して過ごすことが大切です。正しい姿勢や顎の使い方を心がけ、顎周囲に負担がかからないようにしましょう。
また、定期的に歯科医院を受診して、お口周りの健康をチェックすることも有効です。むし歯などによって顎の使い方が偏ってしまうことも顎関節症の要因となりますので、定期的な歯科検診でお口のトラブルを防ぐようにしましょう。
まとめ

顎関節症は、さまざまな要因によって生じるため、何日で治るかというはっきりとした基準はありません。しかし、しっかりと治療に取り組めば数ヶ月から半年程度で改善できるケースが多いので、症状に悩んでいる方は、まずは一度歯科医院に相談してみるとよいのではないでしょうか。
参考文献
