顎関節症になると顎の関節とその周辺にさまざまな症状がおこります。痛み・カクカクという雑音・お口が開けにくいなどの症状が主体です。
これらは2人に1人は経験するともいわれるポピュラーな症状です。なかには音だけで痛くない場合もあります。
本記事では、顎関節症の原因や症状・治療法などを詳しく解説していきます。顎関節症が痛くない場合や罹患しやすい人に関しても紹介するので参考にしてください。
顎関節症で痛くない場合

多くの方が一度は経験する顎関節症ですが、なかには痛い場合と痛くない場合があります。関節症で痛くない場合はどのような状態を指すのでしょうか。
また、痛くない場合でも治療が必要なのでしょうか。ここでは、痛くない顎関節症について詳しく解説します。
顎関節症で痛くないこともありますか?
顎関節症の特徴的な症状は、耳の前方にある顎関節周辺の痛み・関節が発する音・お口が開けにくいことが挙げられます。とはいえ痛くない場合もあるなど、すべての症状が出るとは限りません。
顎関節症と診断される基準は、痛み・音・お口の開けにくさのうち一つがあり、ほかに同じような症状の病気がない場合です。
お口を開閉するときに発する関節雑音のみの症状であれば、たとえ顎関節症を発症していても痛くないことがあります。
痛くない場合は治療が必要ですか?

顎関節症でおこる音は、首や肩を回したときによくあるポキポキ音・カクカク音と同じです。世界的な認識として、この音だけが症状の場合はあえて治療する必要がないとされます。
音だけが自覚できる方は、全人口の20%以上ともいわれるほど多い症状です。また、症状がある方のうち、治療が必要な症例は5%程度と推定されています。
お口を開閉した際に鳴る関節雑音は手術を行えば消せる可能性が高いでしょう。しかし、関節雑音以外の症状が出ていなければ、わざわざ手術を行う必要はありません。
また、現在は関節雑音を消すためだけに手術を行うことはされていないです。
そのため、しばらく様子をみておいて構いません。
しかし、様子をみているうちに症状が強くなりだしたり痛みが強くなったりしたら、早めに歯科医院で受診しましょう。
顎関節症で痛くない場合の注意点を教えてください。
顎関節症がおこる原因はさまざまですが、いきなりおこるわけではなく小さなことが積み重なって生じるケースが多いようです。
たとえ、今は痛くなくても日常生活で何気なくしている癖や習慣で症状がひどくなる場合もあります。日頃から歯を食いしばる癖がある方は、気がついたときに顎の筋肉を緩めましょう。
また、顎への負担を減らすためにも、同じ場所で食べたり噛み続けたりしない・頬杖をしないなど注意しましょう。
顎関節症の症状
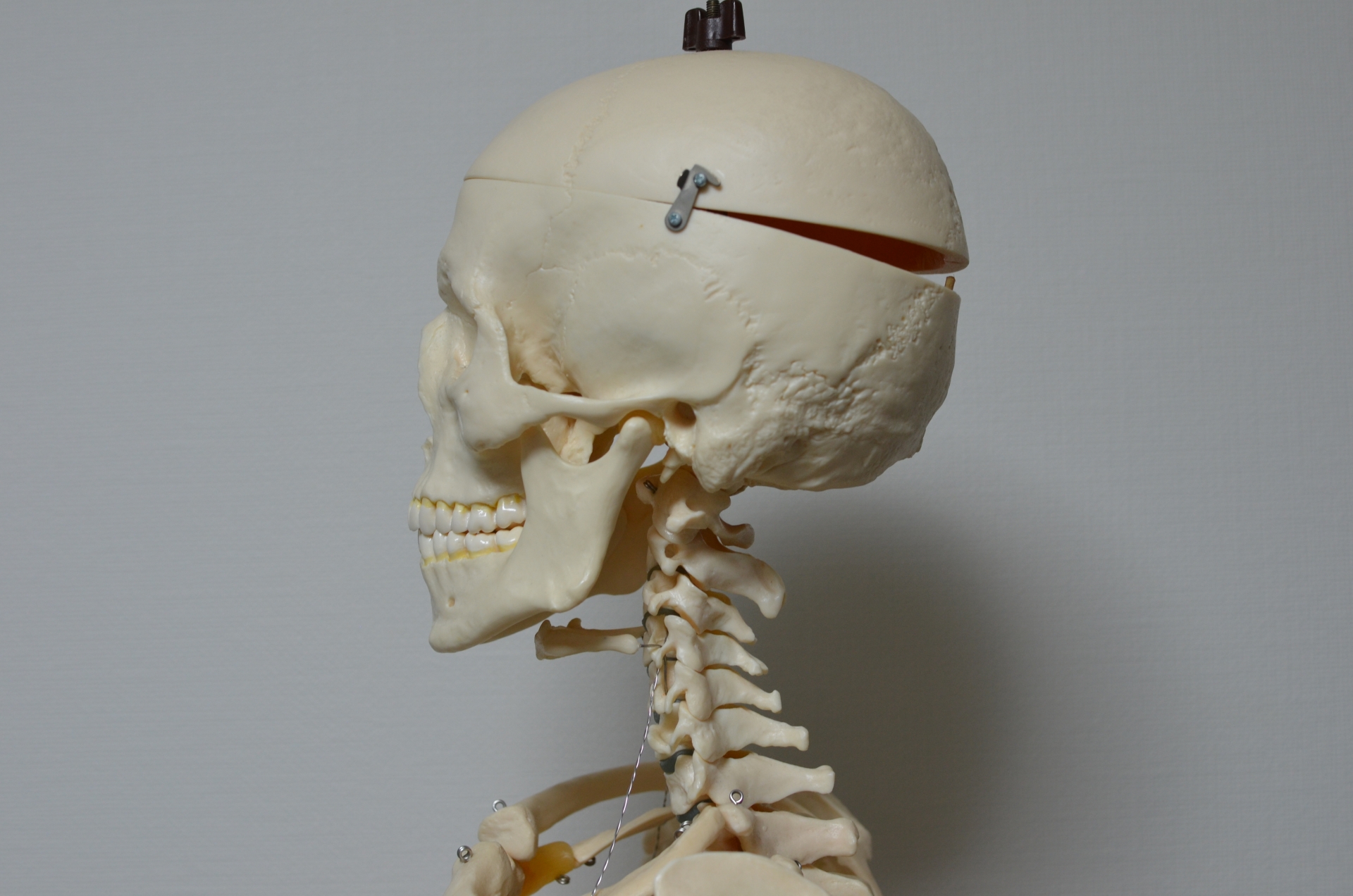
顎関節症になると、顎関節の周辺に痛みや違和感などの症状があります。代表的な症状は以下のとおりです。
- 顎関節の痛み
- 開口しにくい
- 顎関節周囲の圧痛
それぞれの症状を解説していきましょう。なお顎関節の雑音もありますが、一般的に雑音単独では治療対象にならないため省略します。
顎関節の痛み
痛みは顎関節症の代表的な症状です。痛みの出方には顎関節症の症状によっていくつかのパターンがあります。
まず、顎関節内にある緩衝材・関節円盤がずれて変形している場合です。このときお口を開けたり食物を噛もうとしたりすると痛みが出ます。
また、歯ぎしりやTCH(歯列接触癖)で顎に負荷をかけ続けた場合、関節円板の結合組織や靭帯に損傷が起きます。炎症を伴うこともあるでしょう。
顎関節症が長期間続くと、関節が変形して痛みを伴うことがあります。これは関節内の滑膜に炎症がおこった状態で、お口の開閉にも支障が生じやすくなります。
開口のしにくさ
お口を大きく開けにくいことも顎関節症の特徴的な症状です。炎症を併発するなど顎関節の痛みが強い場合、それだけでお口が開けにくくなります。
食いしばり癖などで咬筋や側頭筋に負荷をかけ続けた場合、強い緊張によって筋肉が硬くなり、痛みとともにお口が開けにくい状態がおこります。
原因として多いのが、関節円盤のずれによるものです。顎関節内にある関節円盤は前後に動きやすい構造で、前にずれても後部組織に引き戻されます。
しかし後部組織が弱くなってずれたまま留まると下顎骨の動きを妨害し、その結果お口が開きにくい状態になってしまうのです。
顎関節周囲の筋肉や靭帯の圧痛
関節周辺の咬筋・側頭筋に強い緊張がある場合も痛みが出やすく、このときは顎よりも頬やこめかみのあたりに痛みを感じることが多くなります。
筋肉や靭帯に強い負荷がかかった結果で、手足の捻挫に似た状態です。この場合咬筋や側頭筋は硬くなっていて、しこりのような塊を感じることもあります。
この場合の痛みは何もしないのに痛む自発痛ではなく、押せば痛む圧痛です。
顎関節症の原因

顎関節症になる原因は単純ではありません。さまざまな要因によって噛み合わせに不具合がおこったり、精神的な緊張・ストレスで過剰な力が顎関節にかかったりすることなどが考えられます。
主な原因として挙げられるのは以下のとおりです。
- 過度の開口・あくび
- 硬いものを噛む
- 嚙み合わせの異常
- 歯ぎしり
- 顎関節周囲の異常な緊張
それぞれに関して詳しく解説していきます。
過度の開口・あくび
思いきり大きなあくびをしたりスポーツの応援をしたり、大きくお口を開ける動作を繰り返すことがきっかけで、顎関節症を発症する場合があります。
あくびなどでお口を大きく開けると、強い力で顎の骨や緩衝材の関節円盤が連動します。関節円盤は繊維状で、顎関節の中にあって周囲とゆるくつながった組織です。
急に大きく顎関節が動かされると、関節円盤が前方に押し出されてずれる場合があります。この状態でお口を閉めると音が出ます。
ずれた関節円盤がもとに戻るときにおこるカクカク音です。
また、ずれたまま戻らなくなると顎関節が円滑に動かず、開口障害や痛みなどの症状が出ます。
硬いものを噛む

スルメのような硬いものを噛み続けると、顎関節症の原因になりえます。顎を動かす筋肉・骨に過剰な負荷がかかり、筋肉や靭帯の損傷で痛みが出るのです。
また、過大な力で噛み続けると顎関節内にある関節円盤のずれも発生します。その結果、カクカクという音が出るほか、さらに悪化して現れるのがお口が開けにくい症状です。
噛む力を維持したい場合は、力いっぱい噛むのではなく噛む回数を増やしてください。意識的に硬いものを選んで思いきり噛むのは逆効果で、顎関節症の原因になる可能性があります。
噛み合わせの異常
歯の噛み合わせが正常でない場合、上下の顎にずれが生じています。食べ物を噛むときの力が均等に歯にかからず、左右どちらかの顎に負荷が偏りがちです。
左右の顎の筋肉のバランスが崩れた状態が続くと、負荷がかかる方の顎の筋肉が緊張して痛みが出ます。
以前は噛み合わせの異常が額関節症の主原因とされてきましたが、実はほかのさまざまな要素が絡まる複合的な原因があることがわかってきました。
治療法にも変化があり、従来の歯を削るような歯列矯正は推奨されなくなっています。代わりにスプリントで調整したり、保存療法で対応したりするのが一般的です。
歯ぎしりをする

歯ぎしりも顎関節症の主な原因です。寝ている間に上下の歯を横方向にすり合わせ、ギリギリと音を立てます。昼夜を問わず上下に強く噛みしめる癖である食いしばりも、歯ぎしりの一種です。
歯ぎしりも食いしばりも無意識に行われるため、強い力が長時間にわたって顎関節に加わり続けます。この負荷により、顎関節や周辺の筋肉・靭帯に障害が発生したのが顎関節症です。
歯ぎしりの原因は従来噛み合わせの異常とされていましたが、現在はストレスなど精神的な要因との関連が深いといわれます。
不安や鬱憤を歯ぎしりによって無意識下に発散させると考えられています。ほかには飲酒・喫煙・カフェインとの関連も考えられるでしょう。
顎関節周囲の異常な緊張
耳の前方にある顎関節周辺に痛み・違和感・不快感がある場合、顎関節に付帯する咬筋や側頭筋が過度に緊張している可能性があります。
緊張は慢性的な疲労から来ています。先述した歯ぎしり・食いしばりのほか、TCH(通常接していない上下の歯列を常に接触させる癖)による疲労が原因です。
TCHでは咬筋や側頭筋が常時収縮して上下の歯を接触させるため、慢性的な筋肉疲労をおこしています。その結果過度な緊張状態になり、痛みや違和感など顎関節症の症状がおこるのです。
TCHがある方は歯ぎしり・食いしばりを併発する例が多く、顎関節症の症状のほかに片頭痛や肩こり・耳の痛みなどの症状が見られます。
顎関節症の治療法
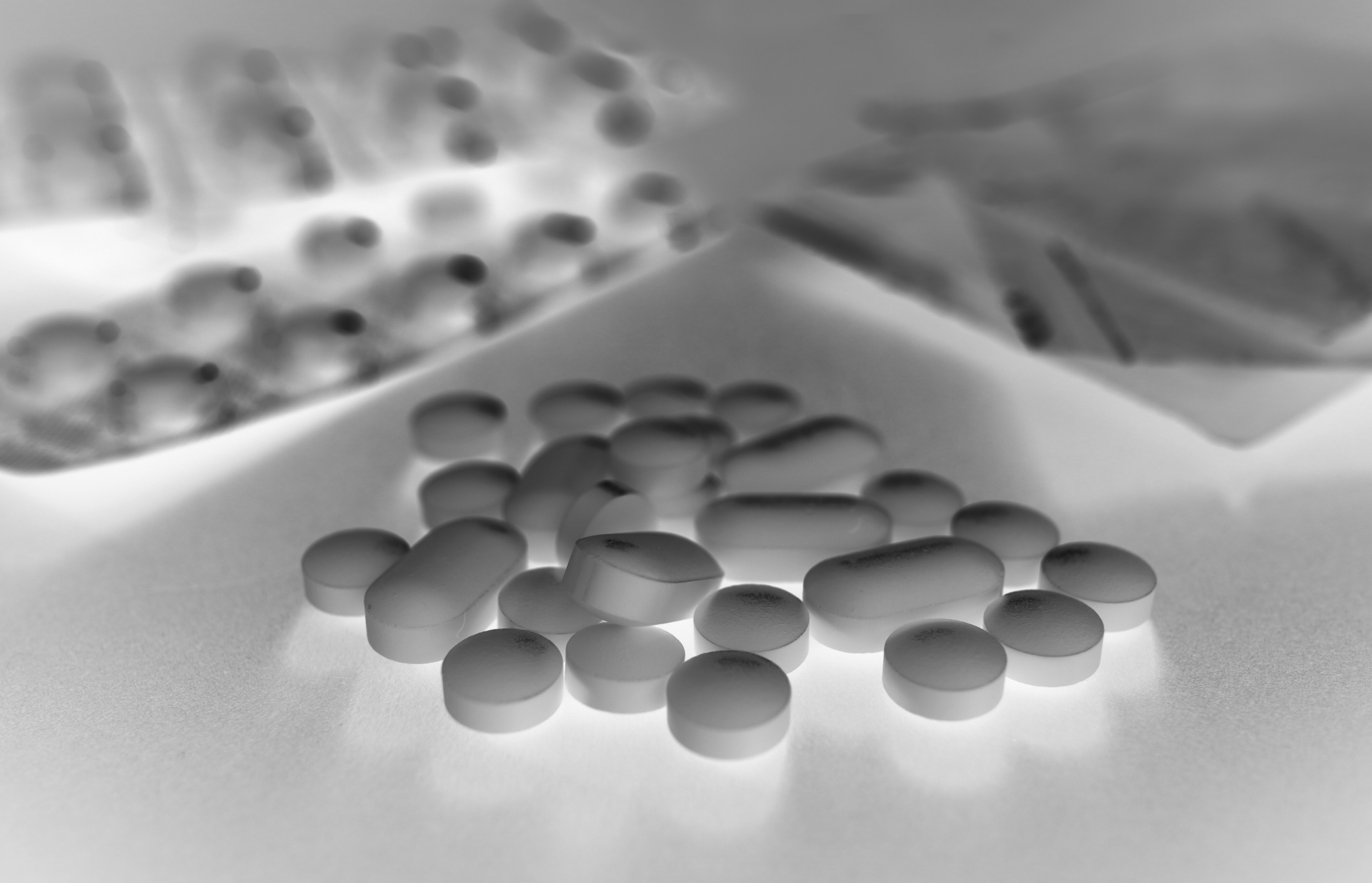
顎関節症は状況によってさまざまな治療法があり、多くの方は手術に至らず回復が期待できます。ここでは有効な治療法をいくつか紹介しましょう。
- 消炎鎮痛薬の使用
- 筋弛緩薬の使用
- 噛み合わせの調整
- 保存療法
それぞれ個別に解説します。
消炎鎮痛薬の使用
顎関節症に対して対症療法的によく使用されるのが、非ステロイド系の消炎鎮痛薬です。この薬剤への評価は、日本歯科薬物療法学会の顎関節症治療ガイドラインで有効とされ使用が推奨されました。
消炎鎮痛薬の顎関節症に対する効果では、開口障害・関節雑音・疼痛などに有効とされています。特に評価が高いのが、関節痛・筋痛・開口痛などの痛みへの効果です。
消炎鎮痛薬による治療効果に関しては、国内で臨床試験が実施されました。
7日間投与した患者さんのうち、関節円盤のずれが戻らないタイプを除いて、約85%の方に症状の軽減または消失が見られたとのことです。
筋弛緩薬の使用

歯ぎしりや食いしばりなど過大な負荷で筋肉が硬くなったタイプの顎関節症では、筋弛緩薬が使われます。筋肉の緊張を和らげることで、痛みや開口障害を軽減する目的です。
顎関節症では咬筋や側頭筋・靭帯の障害に対して使われる薬剤で、効果に関して臨床試験が行われています。
筋弛緩薬を2~4週間服用した後、筋痛に対しては75%で改善が見られました。開口率では正常に近い状態まで回復し、筋弛緩薬の有効性が示されています。
噛み合わせの調整
顎関節に大きな負担を与える歯ぎしり・食いしばりの影響を軽減するため、噛み合わせの調整が行われます。具体的には、就寝中にスプリント(マウスピース)を装着する方法です。
やわらかいプラスチックのスプリントを歯列にかぶせるもので、顎関節や筋肉にかかる負担を弱めて負担を軽減します。鎮痛薬との併用で効果が望める治療法です。
保存療法
顎関節症の症状の多くは、時間の経過につれて軽減されます。そのため最初は顎・歯・顔面に影響を与える治療は避け、保存療法を行うのが一般的です。
広い意味では薬物療法やスプリントも保存療法に含まれます。ほかには赤外線レーザーや電気刺激で血流をよくすれば症状の改善が期待できます。
一方で、歯科医師の指導のもと自分で行うセルフケアも欠かせません。
最初の急性期では冷湿布で安静を保ち極力開口を控えます。落ち着いたら温湿布に変えてゆっくりと開口訓練などを始めます。
指先で行うマッサージや、関節を動かし固まった筋肉を伸ばす運動もおすすめです。日常生活全般で、食いしばりや噛みしめにつながる行動・食事はできる限り避けましょう。
顎関節症に関するよくある質問

顎関節症に関連するよくある質問をいくつか集めました。順に見ていきましょう。
噛み合わせが悪いと体全体の調子が悪くなるのか、気になる方は少なくないでしょう。
噛み合わせが影響するのは、顎の周辺の狭い範囲に限られます。体の広範囲に影響を及ぼすとしているメディアも一部あるようですが、科学的根拠はありません。
顎関節症が治ると肩凝りや腰痛は改善できるのか気になる方もいます。
顎関節症はさまざまな要因が関係しているので、治療で肩こり・腰痛が改善する可能性があります。ただ、因果関係は不明確で、間接的に影響する可能性がある程度です。
そのため、肩凝りや腰痛の治療もかねて歯科医院へ行っても、期待した結果が得られないかもしれません。
顎関節症は専門の先生じゃないとダメだと思われている方もいるのではないでしょうか。
顎関節症治療は特に口腔外科を専門とする医師にこだわる必要はありません。顎関節症の多くは保存療法で治せるので、近くにある一般的な歯科医院でも治療できる可能性が高いでしょう。
もし手術など外科治療が必要な状態ならば、歯科医師が大学病院などに紹介状を書いてくれます。
まとめ

ここまで顎関節症に関して解説してきました。顎の痛み・雑音・開口障害が主な症状で、20歳代の女性に多い病気です。雑音だけで痛くない場合は治療しません。
さまざまな要因が関わり、顎関節や咬筋に過度の負担がかかり発症します。治療は薬剤やセルフケアなど保存的治療が主体で、手術に至るのはごく少数の方です。
普段の生活習慣のなかに原因があるので、顎や咬筋に負担をかけないことを日常的に意識しましょう。もし顎に異変を感じたら、近くの歯科で早期に治療を始めてください。
参考文献
- 顎関節症|日本歯科医師会
- 顎関節症とは|一般社団法人 日本顎関節学会
- 顎関節症|KOMPAS 慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイト
- 「平成 28 年歯科疾患実態調査」の結果(概要)を公表します
- 当科における過去 10 年間の顎関節症患者の後ろ向き調査による臨床統計的検討
- 顎関節|公益財団法人 日本口腔外科学会
- 顎関節症とは…?
- 顎関節症|東京医科歯科大学 顎顔面外科学分野
- 顎関節症の関節痛に対する消炎鎮痛薬診療ガイドライン
- 疼痛を有する顎関節症に対する消炎鎮痛薬の短期的治療効果—症型分類別による治療効果の比較—
- 顎関節症に対する中枢性筋弛緩剤 Afloqualone(アロフト®︎)の使用経験
- 顎関節症患者のための 初期治療診療ガイドライン3
