親知らずは、歯並びや噛み合わせを悪くしたり、手前の歯の歯根を吸収させたりするなど、深刻な症状を引き起こす永久歯ですが、抜歯をした後にも発熱などの厄介なトラブルを招くことがあります。
この記事では、親知らずの抜歯後に熱が出る理由や対処方法、自宅で行えるケア方法について解説します。現在、親知らずの抜歯後の発熱に悩まされている方、これから親知らずを抜歯する予定の方も参考にしてみてください。
親知らずの抜歯後に熱が出る理由
 親知らずを抜いた後に発熱する理由を解説します。歯を抜くことと発熱とは何ら関係がないように思えますが、実際はいくつかの理由があるのです。
親知らずを抜いた後に発熱する理由を解説します。歯を抜くことと発熱とは何ら関係がないように思えますが、実際はいくつかの理由があるのです。
手術後の自然な反応によるもの
親知らずの抜歯は、通常の歯科診療とは異なり、侵襲の大きい治療となることがあります。その結果、手術後の炎症反応として発熱を引き起こしてしまいます。 特に斜めや真横に生えていたり、半分埋まっていたりする親知らずの抜歯では、
- 歯茎をメスで大きく切開する
- 顎の骨を削る
- 親知らずを複数に分割する
このような処置が必要となるため、手術後は自然な反応として炎症が起こります。それが全身の発熱につながったとしても決して不思議なことではありません。
◎腫れや痛みが出るのは患部の周り
親知らずの抜歯後の反応として腫れたり、痛くなったりするのは、基本的に患部の周りに限定されます。親知らずを割る際にハンマーのような器具で叩く処置が行われた場合、手術後に頭痛や倦怠感、発熱が生じることがあります。 こうした症状は、生理的な反応にとどまることから、手術から数日も経過すれば改善していくことでしょう。
ドライソケットによるもの
親知らずの抜歯後、ドライソケットが原因で発熱が生じることもあります。ドライソケットとは、親知らずを抜いた穴(抜歯窩)の治癒が正常に進まず、顎の骨がむき出しとなることで発症する病気です。
本来であれば抜歯窩(ばっしか)には、血餅(けっぺい)と呼ばれるかさぶたができて、穴が徐々に塞がっていきますが、抜歯後に強くうがいを繰り返し行うとその蓋が剥がれて骨の部分がむき出しとなります。
通常であれば、抜歯後の痛みや腫れは2〜3日程度で治まりますが、抜歯から3〜5日経過してから発熱などの症状が現れたら、ドライソケットが疑われます。
◎ドライソケットの症状
一般的な親知らずの抜歯でも、手術から2〜3日は強い痛みが生じます。個人差はありますが、鎮痛剤でも抑えられないような痛みが生じることも珍しくありません。
ドライソケットによる痛みは、さらに痛みが強くなります。鎮痛剤による効果がなかったり、日常生活に大きな支障があったりするケースもあるため注意が必要です。
以下に挙げる症状が認められる場合は、抜歯窩でドライソケットを発症している可能性が高いため、早急に主治医に診てもらいましょう。
抜歯から1週間経過しても強い痛みがある
安静時にもズキズキとした強い鈍痛が続いている
抜歯窩の骨が露出している 抜歯窩から膿が出ている 発熱や頭痛、倦怠感がある
◎ドライソケットを防ぐ方法
ドライソケットは、抜歯後のうがいの仕方で防ぐこともできます。
親知らずを抜いた数日間は、ブクブクと強くうがいをするのは避けるようにしましょう。うがいの回数も控えることが大切です。抜歯窩のかさぶたが定着して、傷口の治癒も進み始めたら、通常どおりにうがいをしても問題ありません。ただし、ドライソケットというのは親知らずの抜歯全体の0.5〜4%程度で発生するともいわれており、こうした対策をとっても予防できないことはあります。
感染症によるもの
抜歯後の発熱では、感染症が疑われます。抜歯後は、患者さんの心身に大きな負担がかかることから、全身の免疫力も低下します。結果として、抜歯後に風邪やインフルエンザのような全身の感染症にかかってしまう可能性も十分にありえます。 また、手術時の衛生管理が不十分であったり、手術後のセルフケアが不適切だったりした場合は、抜歯窩を中心に感染が起こることもあります。親知らずが生えている部分は、鼻腔や喉頭、咽頭などとも近いため、発熱を伴う全身の感染症に発展することもあるでしょう。
親知らずの抜歯後に熱が出ないようにするには
 親知らずの抜歯後は、ただでさえ顎の痛みや腫れに悩まされるところに、発熱まで重なるような事態は絶対に避けたいものです。そこで親知らずを抜歯する方は、次のような点に注意することが大切です。
親知らずの抜歯後は、ただでさえ顎の痛みや腫れに悩まされるところに、発熱まで重なるような事態は絶対に避けたいものです。そこで親知らずを抜歯する方は、次のような点に注意することが大切です。
歯茎や歯周に負担をかけない
抜歯後に歯周組織への負担をかける行為はできるだけ避けるようにしましょう。 患部で食べ物を噛んだり、抜歯窩を歯ブラシで刺激したりするような行為は、術後の感染症のリスクを高めるとともに、傷口の治りも遅らせます。大切なのは「うがいをしすぎない」ことです。親知らずの抜歯直後に強いうがいをすると、抜歯窩の血餅が剥がれてドライソケットを誘発します。 抜歯直後は、血の味がするため、うがいできれいに洗い流したくなるものですが、できるだけ我慢をして傷口が癒えるのを待ちましょう。
治療時間を短くする
親知らずの抜歯後の痛みや腫れの程度は、治療にかかる時間とも関連があるとされています。5分程度の時間で終わる抜歯であれば、治療後の痛みや腫れがほとんど起こらず、発熱もしないことがほとんどです。 一方、親知らずの抜歯に30~60分程度かかるケースでは、歯茎や顎の骨に大きなダメージを受けるとともに、患者さんの心身にも過大な負担がかかることから、治療後に発熱するリスクも高まります。 ただし、親知らず抜歯にかかる時間は、患者さんにはコントロールできません。
歯科医師の技術によって大きく左右される部分なので、治療時間を短くしたい場合は、親知らずの抜歯の治療経験が豊富な歯科医院を探すことが重要となります。大学病院や地域の総合病院であれば、診療体制も整っており、親知らずの抜歯に長けた口腔外科の歯科医師が手術を担当するため、治療時間も短くできることでしょう。
発熱した場合に見られる症状とその対処方法
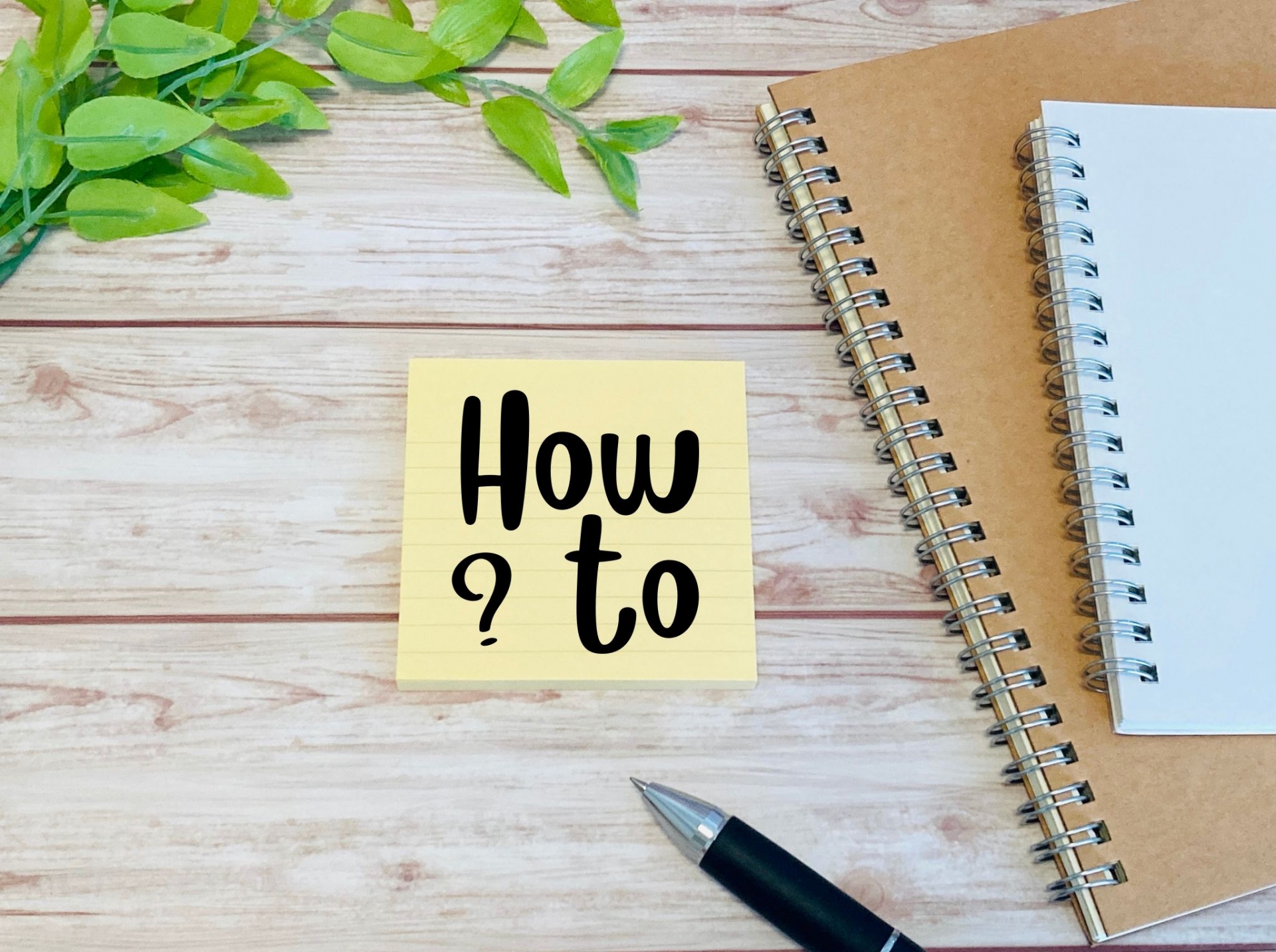 親知らずの抜歯後に発熱した場合、その他に見られる症状によって対処法が少しずつ異なります。
親知らずの抜歯後に発熱した場合、その他に見られる症状によって対処法が少しずつ異なります。
発熱とともに強い痛みがある場合
親知らずの抜歯後の症状が発熱と患部の強い痛みだけであれば、経過観察が推奨されます。親知らずの抜歯後には患部に相応の痛みや腫れ、場合によっては発熱を伴います。これらの症状が親知らずの抜歯後から生じていて、2〜3日くらい継続する程度なら、心配する必要はないでしょう。
発熱と患部の強い痛みが3〜4日経っても寛解せずに痛みが強まったり、その他の症状がある場合は、何らかの異常が疑われるため、主治医に連絡してください。
顔の腫れや膿が出ている場合
発熱や顎の腫れにとどまらず、顔が広範囲に腫れたり、患部から膿が出てきたりする場合は、感染症を引き起している可能性が高いです。
ドライソケットによる症状が原因であれば治療しやすいですが、顔が腫れて膿が出ているということは、顎骨骨髄炎(がっこつこつずいえん)や蜂窩織炎(ほうかしきえん)、上顎洞炎(じょうがくどうえん)などのより広い範囲の感染症を発症している可能性もあります。
これらは歯性感染症(しせいかんせんしょう)と呼ばれるもので、対処が遅れるとより深刻な症状を引き起こしかねないため、抜歯後に顔が大きく腫れたり、膿が出てきたりした場合は早急に歯科を受診してください。
高熱が続く場合や寒気を感じる場合
抜歯後に高熱が出て、寒気を感じるような症状が認められる場合は、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など、全身の感染症を発症している可能性が高いです。
特に親知らずを抜いた部分に大きな腫れや痛みが生じていないのであれば、ドライソケットや患部の細菌感染は考えにくいため、内科の受診をする方がよいでしょう。できれば、親知らずを抜いた歯科医院に電話をかけて、現状を伝えておきましょう。全身の感染症に由来する高熱や寒気は、内科で処方される薬剤を服用することで、改善が見込めます。
食欲不振や全身のだるさが続く場合
親知らずの抜歯は、心身への負担が大きい歯科治療です。患部が腫れて、食べ物を噛むこと・飲み込むことが困難になったり、精神的なストレスで食欲不振に陥ったりするケースも珍しくありません。
こうした心身の不調が全身のだるさを引き起こすこともあるでしょう。親知らずの抜歯から1週間も経過すれば、患部の腫れや痛みが軽くなり、食欲不振や全身の倦怠感も薄れていくものですが、長く続くようであれば主治医に相談しましょう。
風邪などの感染症が原因になっていることもあるので、違和感があれば内科を受診することが推奨されます。
発熱時にできる自宅でのケア方法
 親知らずの抜歯後に発熱した場合は、次の方法でセルフケアしましょう。いずれも対症療法にとどまりますが、発熱による苦痛やストレスを和らげることは可能です。
親知らずの抜歯後に発熱した場合は、次の方法でセルフケアしましょう。いずれも対症療法にとどまりますが、発熱による苦痛やストレスを和らげることは可能です。
冷たいタオルやアイスパックで冷やす
発熱に対しては、冷たいタオルやアイスパックで冷やす方法が効果的です。
風邪やインフルエンザにかかったときと同じように冷やしましょう。顎が腫れて痛い場合は、患部を氷などで直接冷やすのではなく、顎に冷たいタオルやアイスパックをあてるようにしてください。
抜歯窩は外傷を負った状態と同じであり、氷などを直接当てるのは衛生的に良くありません。また、患部を過剰に冷やすと血流が悪くなり、かえって治りが遅くなります。
鎮痛剤を使用する
親知らずの抜歯後の発熱による痛みは、鎮痛剤で軽減できます。
親知らずの抜歯後には、歯科医師から鎮痛剤や消炎剤、抗生剤などが処方されますので、それらを指示どおりに服用しましょう。とりわけ抗生剤は、発熱や腫脹、痛みの有無に関わらず、処方されたものをすべて飲み切らなければなりません。
安静を保って身体を休める
親知らずの抜歯後は、発熱の有無に関わらず安静を保つことが求められます。 親知らずの抜歯後に激しい運動をしたり、熱い湯船につかると全身の血流が良くなって傷口が開くおそれがあるからです。 発熱や痛み、腫れなどの症状が認められるのであれば、抜歯後はすぐに帰宅して、身体を休めることが大切です。無理して仕事をしたり、身体を動かすような活動をしたりすると、健康状態がさらに悪化します。
水分補給
熱があるときは、発汗や荒い呼吸による脱水症状が認められるため、水分補給はこまめに行うようにしてください。
十分な水分を摂取することで、健康状態を維持しやすくなりますし、発汗が促されて熱を下げるのにも役立ちます。補給する水分は普通の水でも問題ありませんが、塩分をはじめとしたミネラルを効率良く吸収できるスポーツドリンクや経口補水液が望ましいです。
症状が長引く場合は歯科医院へ相談
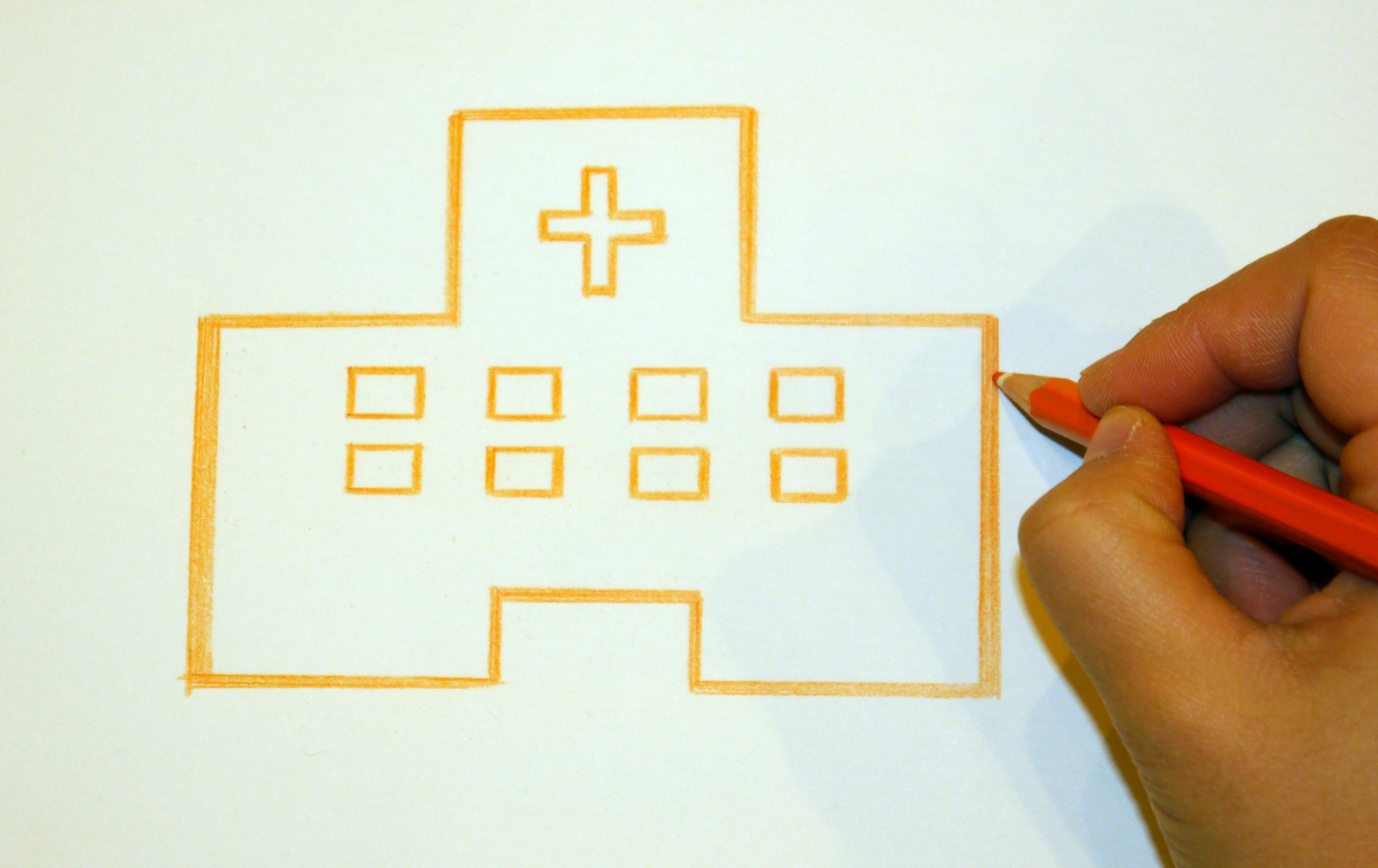 親知らずの抜歯後には発熱や患部の痛み・腫れ、倦怠感など、さまざまな症状が現れます。症状のほとんどは一時的なものであり、親知らずの抜歯に伴う侵襲が原因であるため、過剰に心配する必要はないのですが、症状が長引く場合は注意が必要です。
親知らずの抜歯後には発熱や患部の痛み・腫れ、倦怠感など、さまざまな症状が現れます。症状のほとんどは一時的なものであり、親知らずの抜歯に伴う侵襲が原因であるため、過剰に心配する必要はないのですが、症状が長引く場合は注意が必要です。
ドライソケット、風邪、顎骨骨髄炎、蜂窩織炎など、深刻な病気を併発している可能性が高いことから、不安に感じた時点でまず歯科医院に相談しましょう。親知らずの抜歯を行った場所が大きな病院の口腔外科であったとしても、電話で問い合わせれば主治医につなげてくれます。もしも親知らずの抜歯を行った歯科医院や病院が定休日や診療時間外であった場合は、急患などに対応している近くの医療機関に相談するのもひとつの方法です。
まとめ
親知らずの抜歯後に発熱する原因と対処方法について解説しました。親知らずの抜歯後に熱が出る主な原因は、手術後の生理的な反応、ドライソケットによる症状、何らかの感染症によるものがあげられます。生理的な反応以外は、できるだけ避けなければならないものなので、親知らずの抜歯後の過ごし方は歯科医師の指示に従うようにしてください。
処方された抗菌薬の適切な服用は、親知らずの抜歯後の発熱や感染を防ぐうえで重要です。そうした対策を講じたにも関わらず、親知らずの抜歯後に発熱した場合は、本文でのセルフケアを実施するとともに、症状が長引くようであれば歯科医院に相談しましょう。
参考文献
