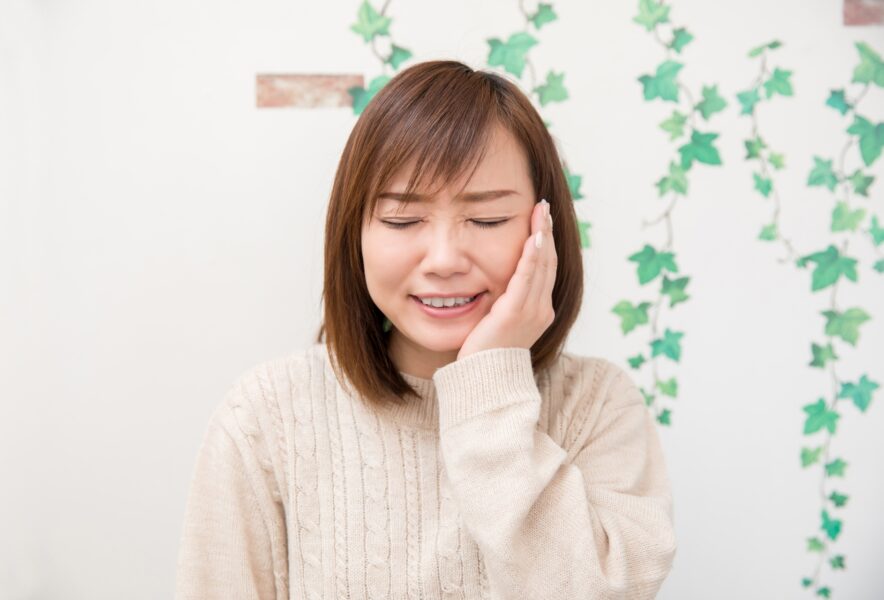顎関節症は、顎の関節や筋肉の痛みや動かしにくさ、顎を動かしたときの雑音などの症状が出る疾患です。
顎関節症は治療して症状が改善したと思っても、再発するケースがあります。では、顎関節症の再発を予防する方法はあるのでしょうか。
本記事では、顎関節症が再発する可能性や再発防止のポイント・治療法を解説します。
顎に痛みや違和感がある方や再発が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
顎関節症は再発するか

- 顎関節症は再発する可能性はありますか?
- 顎関節症は適切に治療すれば症状が改善するケースが多いですが、症状が改善した後も再発する可能性があります。顎関節症になると、主に以下のような症状が現れます。
- お口を動かしたり噛みしめたりすると関節が痛む
- 顎を動かすと関節から雑音がする
- お口をスムーズに開閉できない
治療して症状が落ち着いても、再度上記に挙げたような症状が出て再発を繰り返すことがあり、注意が必要です。顎関節症は無意識のうちにしている食いしばりや歯ぎしりなどの癖、噛み合わせの異常や顎の損傷などが原因とされています。
ストレスがかかると食いしばりや歯ぎしりを引き起こしやすいため、顎関節症はストレス病の一つともいわれています。症状が改善しても、顎に負担をかける生活習慣を続けたりストレスが蓄積したりすると、顎関節症が再発する可能性があるでしょう。
- 再度医療機関を受診する目安を教えてください。
- 顎の関節や周辺の筋肉が痛み、お口を開けにくい場合には日常生活に支障が出てしまうので、医療機関を受診しましょう。顎関節症の主な症状は、顎関節の痛みや雑音、顎関節周囲の筋肉の痛みです。悪化すると、お口を開けにくさや物の噛みにくさ、首や肩のこりなどの症状も出てきます。
顎関節症で現れる症状の程度は個人差が大きく、軽度で済む患者さんもいれば重症化する患者さんもいます。症状が重い状態を放置すると、悪化して顎の機能を失う危険もあるので注意が必要です。
お口を大きく開閉したときに痛みがあったり、お口を大きく開けにくかったりする状態が1週間以上継続するなら、早めに歯科医院を受診しましょう。
顎関節症を再発させないポイント

- 食生活で気をつけることはありますか?
- 再発を防ぐには、食生活で顎に負担をかけないよう気をつけることがポイントです。ビーフジャーキー・するめ・フランスパン・硬い肉など、硬い食べ物はなるべく避けましょう。硬い食べ物は食べる際にしっかり噛みしめなくてはいけないため、顎の関節や筋肉に負担をかけてしまいます。
片側の奥歯だけで噛むと力のかかり方が偏るので、なるべく両側の奥歯で噛むよう心がけましょう。長時間ガムを噛み続けるのも、顎の負担になります。顎に痛みや違和感がある場合は、できる限り顎を安静にして悪化を防ぐことが大切です。
食べ物は小さくカットしてお口を大きく開けないようにし、顎に負担をかけにくいおかゆ、やわらかくゆでたうどん・そばなどを食べましょう。
- 気をつけた方がよい生活習慣はありますか?
- 何気なく行っている生活習慣が顎に負担をかけてしまい、顎関節症の原因になることがあります。顎に負担をかけないよう生活習慣を見直すと、症状の改善や予防につながります。
顎関節症を再発させないために、気をつけたい生活習慣は以下のようなものです。- うつぶせ寝をしない
- 関節や筋肉を冷やさない
- 食いしばりや歯ぎしりを避ける
- 急に顎を動かさない
- あくびをするときはお口を大きく開けすぎない
- 長時間の会話やお口を大きく開ける行動を避ける
- 正しい姿勢を心がける
- 頬杖をつかない
- 爪・筆記用具などを噛まない
- ストレスを溜め込まない
猫背や頬杖・爪かみなどの癖や食いしばりは、無意識に行っていることが少なくありません。上記に挙げた癖や生活習慣は顎に負担をかけて顎関節症を引き起こす可能性があるので、意識して避けましょう。
ストレスで緊張状態が続くと、顎関節周辺の筋肉緊張・食いしばり・睡眠時の歯ぎしりを招いて顎に負担がかかります。ストレッチや自分なりのリラックス方法をとって、ストレスを溜め込まないようにしましょう。
- 顎関節症の再発を防止する方法があれば教えてください。
- 再発防止には、症状が改善した後も顎に負担をかける癖や生活習慣を避けることが大切です。顎関節症の原因はまだ完全には解明されておらず、精神的ストレス・噛み合わせ・骨格・生活習慣など、さまざまな要因が重なると発症するとされています。
ストレスや生活習慣は、気をつければ改善が可能です。なるべくストレスの蓄積や顎に負担をかける生活習慣を避け、顎関節症を引き起こす可能性がある要因が重ならないようにしましょう。
顎関節症の受診や治療法

- セルフチェックできる方法があれば教えてください。
- 普段の生活のなかで無意識のうちに行っている癖が、顎関節症を引き起こすことがあります。自覚症状がなくても、知らないうちに顎関節症になっているかもしれません。顎関節症の確定診断は医療機関で行いますが、顎関節症かどうかセルフチェックする方法もあります。
以下に、顎関節症でよくみられる症状を挙げます。顎に痛みや違和感がある方や顎関節症が心配な方は、あてはまる項目がないかぜひチェックしてみてください。- 物を噛むとこめかみや耳周辺・頬が痛む
- お口が突然開かなくなることがある
- お口に指3本分(人差し指・中指・薬指)が縦に入らない
- お口を開閉すると音がする
- お口を開閉すると痛む
- 物を噛んだり長時間会話をしたりすると顎が疲れる
- 顎が外れることがある
- 頭痛や肩こりがよく起こる
複数の項目があてはまる場合は、顎関節症の可能性があります。気になる症状が続く場合は、悪化する前に早めに医療機関を受診しましょう。
- 顎関節症は何科を受診すればよいですか?
- セルフチェックで顎関節症にあてはまる症状があった場合は、口腔外科を受診するとよいでしょう。病院によっては、顎関節症外来を設けているところもあります。顎関節症では関節や耳周辺の痛みが生じるため、耳鼻咽喉科や整形外科を受診する患者さんもいますが、顎関節症を専門に診療するのは口腔外科です。
顎関節症かどうかわからない場合や症状が軽く悪化していない場合は、まずはかかりつけの歯科医院に相談してもよいでしょう。状態によって、顎関節症の専門医療機関を紹介してもらえます。
- 治療法を教えてください。
- 顎関節症の治療は、薬物療法・スプリント療法・行動療法などの保存療法が基本です。治療をする前に、問診やX線検査、MRI検査などを行います。X線検査は下顎の骨の異常、MRI検査は関節円板の位置・関節内の炎症をチェックする検査です。
検査の結果、似た症状が出るほかの疾患を除外して顎関節症と診断されると、顎関節症の治療を始めます。顎関節症の保存療法では、以下のような治療をします。- 薬物療法:消炎鎮痛薬・筋弛緩薬で関節や筋肉の痛み・炎症・緊張を抑える
- スプリント療法(マウスピース):噛み合わせ調整・筋肉の緊張緩和・顎への負担軽減を図る
- 行動療法:顎に負担をかける生活習慣を見直します
- パンピングマニピュレーション:麻酔をしたうえで顎を手で動かし、関節円板のズレや癒着を改善する
- 関節腔洗浄:関節内の炎症がひどい場合、生理食塩水で内部を洗浄する
- 開口訓練によるリハビリ
- 理学療法:筋肉のストレッチやマッサージ(マイオモニターによる電気マッサージなど)で血行を促進し、筋肉の症状を軽減する
スプリント療法はマウスピースを夜間に装着し、噛み合わせを調整して睡眠中の歯ぎしりを防ぐ治療法です。
顎関節症を治療するうえでは、薬物療法やスプリント療法に加えて行動療法で生活習慣を見直し、なるべく顎に負担をかけない生活を心がけることが大切です。
- 顎関節症で手術が必要なケースもありますか?
- 保存療法で改善がみられない場合や関節円板の癒着がひどい場合には、手術が必要になるケースがあります。
多くの患者さんは保存療法で症状がよくなり、手術が必要なケースは顎関節症の患者さん全体の数%程度です。
手術では、内視鏡を使用する関節鏡視下剥離受動術や、関節を切開する外科手術が行われます。噛み合わせのズレがひどい場合には、手術を伴う歯列矯正治療をするケースもあります。
編集部まとめ

本記事では、顎関節症の再発の可能性や再発させないポイントと治療法を解説しました。
顎関節症は、治療で症状が改善した後も再発する可能性があります。
顎関節症の再発を防止するには頬杖や食いしばり、うつぶせ寝などの顎に負担をかける生活習慣の見直しが重要です。
顎関節症の要因となる癖や生活習慣に心あたりがある方は、予防のためにもぜひ意識して改善しましょう。
参考文献