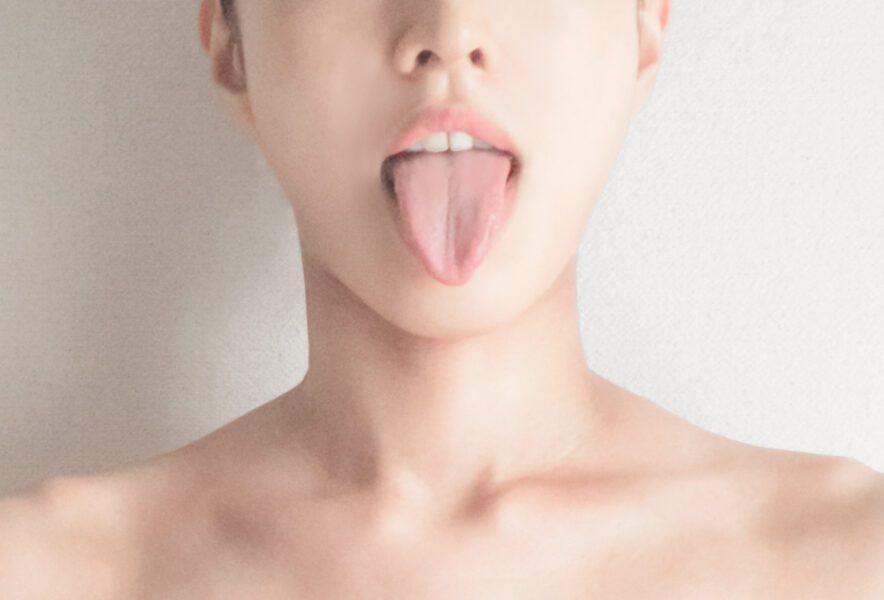舌に痛みが出ると、舌がんではないかと不安になる方もいると思います。悪性腫瘍の一種である舌がんは、症状の進行により痛みやさまざまなトラブルを引き起こします。
この記事では舌がんによる痛みがどのように生じるのかや、舌がんと診断された場合の治療方法などについて詳しく解説していきます。
舌がんの特徴と痛みの現れ方

まずは舌がんがどのような病気であるのか、その特徴や痛みの現れ方を解説します。
舌がんとは
舌がんは、その名前のとおり舌にできるがん(悪性腫瘍)のことを指します。
腫瘍とは身体の細胞に何らかの異常が生じて過剰な細胞分裂が行われることによって大きな塊ができるものです。腫瘍には良性と悪性があり、ほかの臓器に転移するなどして重大な問題を引き起こす可能性があるものが悪性、そうでないものが良性と分類されます。 舌がんができる範囲は舌の前方3分の2の範囲で、口を大きく開いたときに見える部分です。これよりも後ろ側である舌根部にがんができた場合は、咽頭がんと分類されます。
舌がんの多くは舌の側面に生じ、舌表面などにできることは稀です。 お口のなかにできるがんを総称して口腔がんと呼びますが、口腔がんの内の約60%が舌がんで、60代など高年齢で発症しやすい一方、20代の若年層などでも発生する場合があります。
舌がんの初期症状
舌がんは初期症状で痛みなどの自覚症状が現れにくい疾患です。そもそも腫瘍は全般的にそうなのですが、元々ある自分自身の細胞が増殖して生じるものであるため、炎症や出血などが起こりにくく、痛みなどの自覚症状がすぐにはでません。
はじめに自覚症状として現れやすいのはしこりで、舌の一部に硬い固まりがあるような感覚が生じます。また、見た目では舌の粘膜が白くなったり、赤くただれたりといった変化がみられる場合もあります。
舌がんによる痛み
舌がんが進行して腫瘍が大きくなると、痛みや出血が生じることがあります。痛みについては舌を動かしたり、何か物に触れたりしたときなどに現れやすく、口内炎に似たような痛みを感じます。
舌がんを放置した場合のリスク
舌がんは、周囲の細胞を巻き込みながら拡大していく悪性腫瘍の一種です。症状を放置しておくとサイズが大きくなっていき、舌やお口を動かしにくくなり、生活に支障が生じます。
また、がん細胞は血流などによって身体のほかの部位に転移する場合があり、特に舌がんをはじめとした口腔がんは、頸部リンパ節という首のリンパ節に転移しやすいことが知られています。
頸部リンパ節は身体の免疫機能を高める役割を持つため、ここに転移してしまうと、全身の免疫力が低下することにもつながります。
場合によっては肺などほかの臓器に転移することもあり、転移箇所が多くなると治療が困難となるため、生命に関わるリスクが増大します。
歯科口腔外科を受診すべき症状

舌がんは、お口のお悩みに対して行う外科治療を専門的に取り扱う、歯科口腔外科で専門性の高い診療を受けることができます。
舌の痛みをはじめ、下記のような症状がある場合には、歯科口腔外科の診療を行う医療機関を受診するとよいでしょう。
痛みのない口内炎のような腫れ
お口のなかにできる炎症を総じて口内炎とよびます。口内炎は細菌やウィルスなどの影響によって生じ、腫れや痛みが出る症状です。
舌に腫れができるという点では口内炎と舌がんで同じような症状であり、口内炎であれば放置しておけば自然に治るため、放置してしまう方が多いと思います。
注意したいのは、腫れがあるのにも関わらず痛みが出てこない場合で、一定期間にわたって腫れやしこりがあるのに痛みがなかなか現れない場合は、舌がんの疑いがあります。
2週間以上続く舌の口内炎のような症状
口内炎の場合、その多くは発症から2週間程度もすれば軽快し、痛みや腫れが自然と引いていきます。一方、舌がんの場合は自然に症状がおさまることが少なく、痛みや腫れが徐々に強まっていきます。
できたと思ってから2週間が経過しても治らない口内炎がある場合は、早めに歯科口腔外科を受診しましょう。
舌の白い病変
舌の表面が白く濁るのは舌苔とよばれるものの影響ですが、それとは別に、明らかに白い病変がみられるような場合や、赤くただれているような場合には、歯科口腔外科を受診しましょう。
舌がんでなかったとしても、早期に原因を調べて治療を受けることで、身体への負担を抑えて改善できる可能性が高まります。
舌がんと間違いやすい症状

舌に生じる病変は、舌がんだけではありません。舌がんと間違いやすい症状には下記のようなものがあります。
口内炎
舌をはじめ、お口のなかに炎症が生じ、腫れや痛みが現れる口内炎は、舌がんと間違いやすい症状の代表です。
口内炎は口腔内の細菌やウィルスなどの影響、そして舌を噛んでしまった場合の傷などさまざまな要因でできやすく、人によっては頻繁に口内炎ができることもあります。
ただし、上述のとおり口内炎は発生から2週間以内には軽快する場合がほとんどなので、長期的に治らない口内炎があると感じたら、早めに歯科口腔外科を受診しましょう。
紅板症
お口のなかの粘膜に境界が明瞭な赤色の病変が出現する症状を紅板症と呼びます。場合によっては腫れや潰瘍が生じ、その部分に何かが触れたりすると痛みがでます。
紅板症の原因は正確には判明していませんが、喫煙や飲酒による刺激のほか、粘膜の健康を維持するビタミン類の不足、歯や補綴物などによる刺激といったものが発症の要因になると考えられています。
紅板症自体はがんではありませんが、放置しておくと高い確率でがんになる可能性があるため、手術による治療などが推奨されます。
白板症
口腔内の粘膜の上皮部分が何らかの影響で厚くなり、その影響で白く濁ったような状態に見える状態が、白板症です。こちらもお口の粘膜に対する刺激や、栄養不足などが要因になると考えられています。
粘膜が白く濁る症状にはカビの付着によるものなどもあり、その場合は表面を擦るととれますが、白板症の場合は粘膜の上皮が厚くなっているため、擦っても変化はありません。
細胞の異常な増殖という点からもがんの前段階として考えられ、放置しておくとがん化する場合があります。
扁平苔癬
扁平苔癬は、口腔内の粘膜にレースのような白癬や赤い斑点などがみられる病変です。見た目の特徴がさまざまで、びらんやしこり、水疱などを伴うケースがあります。
根本的な改善が難しい難治性の症状であり、治療は痛みなどの症状を緩和することが主要な目的となります。
原因は明確になっていませんが、ストレスや口腔内への刺激のほか、C型肝炎や糖尿病といった疾患が影響している可能性も示唆されています。
慢性的な角化異常を伴う病変で、放置しているとがん化することもあるため、早めに診断と治療を受けることが大切です。
舌痛症
舌に痛みを感じるものの、舌自体に特に異常が見られない症状を、舌痛症と呼びます。舌にヒリヒリまたはピリピリとしたような痛みを感じますが、明らかな原因疾患がないという状態です。
体質や精神的な影響で生じるものと考えられていて、原因が不明であるため、治療は痛みを抑える薬などによる対症療法か、心療内科的な対応が試みられます。
その他の舌の痛みや赤みを伴う症状
上記のほかにも、口腔カンジダ症や天疱瘡といった症状であったり、体内の鉄分や亜鉛、ビタミンなどが欠乏することで舌に赤みや痛みを生じるといった場合などがあります。
いずれにおいても症状を改善するためにはしっかりとした検査が重要となりますので、舌に痛みや赤み、白い病変などがある方は、早めに歯科口腔外科を受診するようにしましょう。
舌がんのリスク要因

舌がんは、下記のような要因で発症しやすくなることがわかっています。
喫煙習慣
舌がんを含め、口腔がんにおける主なリスク要因として挙げられるのが喫煙習慣です。
タバコの煙に含まれる有害物質による刺激や、喫煙によって口腔内の血流が悪化して免疫力が低下することなどがその理由と考えられています。
非喫煙者に比べて喫煙者が口腔がんにかかる確率は2.4倍ほどになるとされ、喫煙年数や本数が増えるとよりリスクが高まることが判明しています。
飲酒
舌がんなど、口腔がんのリスクを高める要素として、喫煙と同じく強く指摘されているのが飲酒の習慣です。
日常的に飲酒をする方が口腔がんにかかる可能性は、お酒を飲まない方の2.2倍になるとされ、週に300グラム以上のアルコールを摂取する方では3.8倍にもなるという研究データがあります。
喫煙と飲酒を両方とも行う方は特に口腔がんのリスクが高く、飲酒量が多い喫煙者は、飲酒量が少なく喫煙しない方と比べ、口腔がんや咽頭がんのリスクが4.1倍になるという報告がされています。
ウィルス感染
近年になって、舌がんの発症にHPV(ヒトパピローマウィルス)への感染が関与していることが判明しています。
HPVは子宮頸がんの原因になるウィルスとしても知られていて、性行為などによって感染する可能性があります。
不衛生な口腔状態
舌がんは、舌が刺激を受けやすいと発生しやすくなる疾患です。お口のなかが不衛生な状態の方は、口腔内で細菌が繁殖しやすく、細菌の作り出す毒素や酸などによって刺激を受けやすくなるため、がんのリスクが高まります。
歯並びや噛み合わせ
歯並びや噛み合わせが悪く、舌に刺激が生じやすいという場合も、舌がんのリスクを高めます。
また、歯並びが悪いと歯磨きによるケアでの磨き残しが生じやすくなることから、口腔内が不衛生な状態となり、これも舌がんのリスクを高める結果につながります。
舌がんの治療方法

舌がんと診断された場合、医療機関では下記のような方法で治療が行われます。
原発巣切除術
舌がんに対する基本的な治療方法は、原発巣切除術と呼ばれる手術治療です。これは簡単にいえば、がん化している細胞をそのまま切除して取り除くという治療法で、がんの大きさが小さいほど体に負担が少なく、がんが大きくなるほど切除する範囲が大きくなるため、身体への負担も大きい手術となります。
がんは周囲の細胞を巻き込んでがん化しながら拡大していくため、がん細胞をすべて除去しきらないと、がんを完治させることはできません。場合によってはがん化しかけている細胞などが存在する可能性もあり、原発巣切除術はがんと診断されている範囲よりも少し広めの範囲を切除する方法が一般的です。
舌がんの場合、症状の程度に応じて、舌半分や舌全体の切除、または顎などを含む範囲の切除などが行われます。
頸部郭清術(けいぶかくせいじゅつ)
舌がんは、近い位置にある頸部リンパ節(首のリンパ節)に転移しやすいがんです。
頸部リンパ節に転移してしまっている場合は、転移先も含めてすべて除去をしないと、がんを完治させることができません。そのため、頸部郭清術とよばれる方法で頸部リンパ節を切除し、がんの進行を食い止めます。
なお、がんが明確に頸部リンパ節に転移していない場合でも、状況によって転移の可能性が高いと判断される場合には、予防的に頸部郭清術が行われることもあります。
化学療法
抗がん剤などの薬物や、放射線による治療を総称して化学療法と呼びます。
抗がん剤はがん細胞の増殖を抑えたり、がん細胞の縮小効果が期待できる薬品で、内服や点滴などによって投与することで症状の軽快を目指します。
放射線治療は、細胞を死滅させる働きをもった放射線をがん細胞に照射するもので、がん細胞を死滅させることで治癒を目指すものです。
現在のところ、がん細胞だけを選択的に処置する方法はないため、化学療法は治療による副作用も加味しながら、症状の程度や患者さんの状態に応じて行われます。
再建手術
手術によってがんを除去する場合、切除する範囲によっては日常生活に不都合が生じる可能性があります。
舌がんの場合は舌そのものが切除対象となるため、場合によっては食事や会話が十分に行えなくなる可能性があります。再建手術は切除した組織を回復させるための治療で、身体のほかの部位から組織を採取し、必要な機能が満たせるように形を整えて再建が必要な箇所に取り付ける方法によって行います。
まとめ

舌がんは、初期症状の進行によって痛みや腫れが生じる病気です。症状が口内炎に似ていることから、違和感があってもなかなか医療機関を受診せず、長期間にわたって症状が治らないことから歯科口腔外科などを受診して初めて気が付くということもあります。
舌がんを治療するためには、がん化している細胞をすべて取り除く必要があり、がんが進行して範囲が広がってしまうと、それだけ治療も困難になります。
舌がん以外にも舌に痛みがでるような症状はありますが、いずれにしても早めに適切な診断と治療を受けることが健康のための重要なポイントですので、気になる症状がある方は、まずは歯科口腔外科を受診してみてはいかがでしょうか。
参考文献