顎変形症には、軽度から重度の症状までさまざまな状態があり、それぞれ特徴や治療法などが異なります。症状によっては手術治療が必要となることもありますが、大がかりな手術は怖いなど、なるべく手術以外の方法で改善したいという方も多いのではないでしょうか。
この記事は、顎変形症の具体的な症状や原因、症状別の治療法などについて解説します。
顎変形症の概要

顎変形症とは、上下の顎の形状や大きさ、位置、そしてバランスといった部分に何かしらの問題があり、噛み合わせのトラブルや発音などに関する障害、顔貌の変形といった症状が現れるものです。
症状には軽度のものから重度のものまでさまざまで、軽度であれば日常生活において不便さを感じることが少ないといえますが、重度の場合はQOLを著しく低下させる要因になる可能性もあります。
顎変形症によるトラブルやリスク

顎変形症は、下記のようなトラブルやリスクにつながります。
食事がしっかりと噛めない
顎変形症によって噛み合わせが悪くなっている場合、咀嚼が適切に行えず、食事の質が低下してしまう場合があります。
特に、硬いものや弾力があって噛みにくいものなどをしっかり噛むことができず、食事内容の偏りにつながることも多いといえます。
食事内容の偏りだけではなく、そもそも十分な咀嚼が行えないことで消化や吸収がされにくくなってしまうため、栄養不足や消化器への負担増大が生じやすくなります。 また、良好な噛み合わせであれば歯の全体を満遍なく使って噛めるため、負担を分散させることができますが、顎変形症の場合は食事の際に噛みやすい部分ばかりを利用するようになりやすく、歯への負担が偏りやすいという特徴があります。
噛むという強い力がかかる行為をいつも同じ歯で受け止めるようになるため、歯や歯を支える歯槽骨がダメージを受けてしまいやすく、歯が折れたり、歯肉退縮を起こしたりする可能性があります。
顎関節症になる可能性がある
顎関節症は、顎の関節にトラブルが生じることでお口を開きにくくなったり、顎を動かした際に痛みが生じたり、お口を動かすとカクカク音がなるようになったりする症状です。顎の関節の炎症や、関節円板と呼ばれる関節を動かす際のクッションの役割を果たす組織がずれることなどで生じます。 同じ顎に生じるお悩みであるため顎変形症と顎関節症は混同されることもありますが、顎変形症は骨格の変形による症状であり、別物です。
しかし、顎関節症は噛み合わせの悪さによって顎の関節に強い負担がかかり続けることなどが原因の一つであるため、顎変形症が顎関節症を引き起こす要因になり、併発してしまう可能性があります。
見た目のコンプレックスにつながる
顎変形症による顔貌の変化は、見た目のコンプレックスにつながりやすいといえます。場合によっては強い精神的なストレスにより、心の不調が生じてしまう可能性もあります。
顎変形症のタイプ

顎変形症は、顎の形状によってさまざまなタイプがあります。
上顎前突(出っ歯)
上顎前突は、上顎が前方に突出しているような見た目の状態です。
上の前歯が前方に突出したような形状になるため、一般的に出っ歯と呼ばれることもあります。なお、出っ歯は前歯の傾きによっても生じるものであり、上の前歯が大きく外向きに倒れていると、顎変形症ではなくても出っ歯になることがあります。
上顎が突出している分、下の歯を完全に覆うような深い噛み合わせになることもあり、顔を正面からみると四角い輪郭の顔立ちになることもあります。 上顎前突は、下顎が奥に引っ込んだ状態であるため、お口が閉じにくくなり、常に半開きの状態になってしまい、ドライマウスなどの要因にもなります。
また、お口を閉じようとすると顎に力が入ってしまうため、下顎の先端(オトガイ)部分に梅干しジワと呼ばれるしわが入りやすくなる点も上顎前突の特徴です。
下顎前突(受け口)
下顎前突は、上顎前突と逆で下顎が前方に突出している状態です。一般的に受け口やしゃくれ顎とも呼ばれます。
顎変形症のなかでも頻度が高く、下の歯が上の歯よりも前方に出てしまう反対咬合のトラブルになりやすい形状です。 下顎前突は見た目のコンプレックスにつながりやすいほか、発音や活舌に影響しやすく、サ行やタ行の発音がしにくくなりやすいという特徴があります。
開咬
開咬は、奥歯を噛み合わせたときに上下の前歯が開いてしまう状態です。前歯で咀嚼をすることができないため、食事の切断などが上手にできないトラブルが生じます。
歯の成長が不十分になってしまうことや、顎変形症による顎の骨の垂直的な位置の不正などが原因で引き起こされます。
小下顎症
小下顎症は、下顎の骨の発育が不十分で、正常な状態よりも小さいままとなってしまう顎変形症の症状の一種です。下顎全体が小さいのではなく、顎先のオトガイ部分だけが小さくなるようなケースもあります。
また、上顎とのバランスによっては上顎前突の状態になります。 小下顎症は下の歯の歯並びにトラブルを生じさせやすいほか、口腔内において舌を格納するためのスペースが不十分になるため、舌が喉側に落ち込みやすくなり、睡眠時無呼吸症候群などのトラブルにつながりやすいという特徴があります。
顔面非対称
顎の中心線が左右にズレているなどで、顔の左右が非対称になる状態が、顔面非対称です。
顔は表情筋の癖などによって左右完全な対称になる場合の方が少ないといえますが、骨格の影響で明らかに左右差がある状態が顔面非対称とされます。
顔面非対称の方は、下顎前突や開咬などのトラブルも併発することが多いといえます。
ガミースマイル
ガミースマイルは、お口を開けて笑った際に、上の歯茎が見えやすい状態を指します。
笑ったときに2㎜または3㎜以上歯茎が見えるような状態がガミースマイルとされ、見た目のコンプレックスから笑うことができなくなるなどの問題につながります。
顎変形症の原因

顎変形症は、下記のようなさまざまな原因によって生じる可能性があります。
遺伝
顎変形症は骨格の形状が原因となって生じるものであり、遺伝による先天的な影響が大きい症状です。
特に、小下顎症や下顎前突などは遺伝の影響を受けやすく、両親の顎に該当する特徴がある場合、子どもも同じような顎変形症の症状が出やすいといえるでしょう。
生活習慣
顎の骨格は遺伝の影響を受けますが、遺伝だけで骨格などがすべて決まるわけではありません。
顎は生活するうえでのさまざまな影響を受けて発達するものであり、特に顎が発達していく成長期における食事による顎への刺激などは、顎の形状に影響を与えやすいといえるでしょう。食事の際にはよく噛んで顎の筋肉をしっかりと使うように意識することが大切で、顎に適切な刺激が加わることで、成長が促されます。やわらかい食事が多く、咀嚼による刺激が十分でない場合は、顎が発達しにくくなり、顎変形症のリスクが高まる可能性があります。 また、頬杖やうつ伏せ寝など、顎周囲に強い負担がかかるような生活習慣も、顎変形症の要因となります。
顎変形症を予防するためには、健康な顎の発達を促す生活習慣を身に着けることが重要となりますので、できれば小さい子どものうちから歯科医院を受診して、注意するべきポイントなどの指導を受けるようにしましょう。
外傷
事故による外傷なども、顎変形症を引き起こす要因の一つです。外傷そのものではなく、治療後のケアなどによって顎変形症が生じてしまうケースもありますので、治療を受けた後はケアやリハビリまで含めてしっかりと対応するようにしましょう。
顎変形症の治療法

顎変形症の治療法は、症状の内容や程度によっても異なります。
ここでは軽度の症状の場合と、症状が進んでいる場合それぞれの治療法を解説します。
軽度の場合
顎変形症が軽度である場合は、歯列矯正で歯並びを整えることで改善できる可能性があります。
例えば上顎前突による出っ歯や、開咬などの歯並びでのトラブルを治療することで、噛み合わせを整えて顎変形症によるお悩みを解消に導きます。
ただし、歯列矯正はあくまでも歯並びに対する治療であるため、顎変形症による顎の骨格変形については改善することができません。
そのため、歯列矯正で対応ができる範囲は、骨格部分のトラブルが少ない、軽度の顎変形症に限られます。 なお、成長期にある子どもが治療を受ける場合は、歯列矯正の一環として行う顎の拡大などで顎変形症を改善できる場合もあります。
顎が成長段階にある子どもの歯列矯正の場合、歯をきれいに並べるためのスペースを作るために専用の装置を使用して顎のスペースを広げる対応を行うことがあり、これが顎変形症の治療につながります。
骨格への働きかけは、顎が成長段階にある成人前のタイミングを過ぎてしまうと難しくなるため、顎変形症の改善も含めて治療を受けたいという方は、早めに診療を受けることをおすすめします。
症状が進んでいる場合
顎変形症が軽度ではなく、症状が進んでしまっている場合は外科手術を含む治療が行われます。
顎の骨の一部を切断してから金属製のプレートなどで固定して骨の再生を促す手術などがあり、症状に応じた手法で顎の形状を整えます。 重度の顎変形症の場合、骨格の位置を手術で整えるだけでは良好な噛み合わせが得にくいため、手術の前後に歯列矯正も行われます。
歯列矯正は通常であれば保険適用外の治療ですが、顎変形症の治療として手術に組み合わせて行われる場合で、顎口腔機能診断施設での治療の場合は保険適用で受けることができます。
顎変形症の治療で行われる手術の種類

顎変形症の治療として行われる手術には、下記のような種類があります。
上顎骨切り術(ルフォー1型骨切り術)
上顎骨切り術は、鼻の横辺りから水平に骨を切り、上顎の骨を歯ごと全体的に移動する手術です。ルフォー1型骨切り術とも呼ばれます。
上顎の骨を動かすことで、上顎前突や下顎前突、ガミースマイルなどの顎変形症を改善します。
中顔面を修正し、人中を短くするなどの効果もあるため、美容整形の施術として行われることもあります。
切開は歯茎から行われるため、顔の表面に傷が生じることはありません。
骨を移動させた後はチタン製のプレートや、時間経過とともに体内に吸収される材料のプレートなどが用いられ、チタン製のプレートの場合は希望に応じて抜去術などが行われることもあります。
下顎骨切り術
下顎骨切り術は、下顎の骨を奥歯の後ろ辺りで切断し、骨を削るなどして短縮してから固定しなおす手術です。
下顎前突の改善などを目的として行われます。
分節骨切り術
分節骨切り術は、前から4番目または5番目の小臼歯を抜歯してから、上下の前歯部分だけを切り出し、抜歯した部分の骨を削って再度つなぎ合わせる手術です。
抜歯するスペース分、上下の歯を後方に移動させることができます。
オトガイ形成術
顎先のオトガイ部分の骨を切って移動させる手術がオトガイ形成術です。
余分な骨を切除してつなぐことで顎先を短くしたり、前方に移動させて下顎の先端を前方に出したり、左右対称に調整したりすることができます。
一般的な外科的矯正治療の流れ
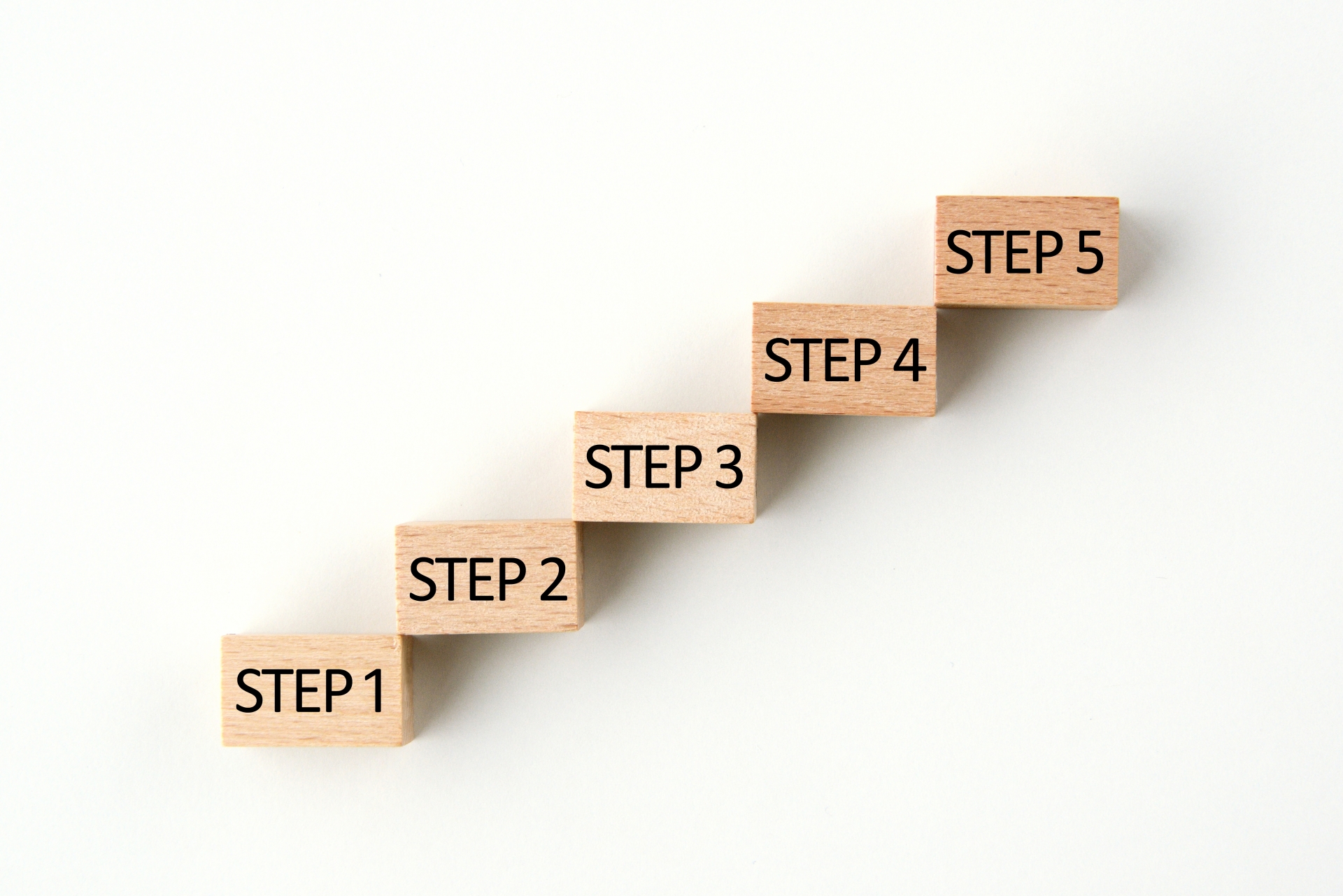
顎変形症の治療として外科的矯正治療を行う場合、一般的に下記の流れで治療が進められます。
術前矯正
外科的矯正治療を行う場合、手術による治療を行う前に、歯列矯正を実施します。これは、手術を行った後に適切な噛み合わせを手に入れられるようにするためのもので、先に歯並びを修正してから骨格を治療することで、手術直後に良好な噛み合わせが得られるように進められます。
そのため、術前の歯列矯正を行う際は、治療を開始する前よりも噛みにくくなる可能性があります。
歯列矯正は1~2年ほどかけて、ワイヤーによる歯列矯正装置によって行われます。
手術
歯並びが整ったら、骨格を修正するための手術を実施します。
骨を切る大がかりな手術であるため、全身麻酔下で行われることが多く、手術前には血液検査などさまざまな検査も実施されます。
手術前後は入院しながら安静に過ごし、手術から数日から数週間程度で退院となります。
術後矯正
手術が終わったら、しっかりとした噛み合わせを獲得するための術後矯正が行われます。1年ほどかけて歯並びを修正していきます。
保定
歯並びが目的の状態に整ったら、後戻りを防ぐために保定を行い、治療が完了します。
先に手術をする方法もある
顎変形症の治療として、術前の歯列矯正を行わない、または短い期間だけ行い、早めに手術を進めるという治療法が行われることもあります。
先に手術をすることで早めに顎変形症の見た目を改善できるメリットや、トータルでの治療期間が大幅に短縮できるといったメリットがあります。
ただし、先に手術を行う方法は保険適用が認められていないため、自費診療での対応となる点に注意が必要です。
顎変形症の治療の費用相場と保険適用

顎変形症の治療は、顎の手術に加えて手術前後の歯列矯正や入院などが必要となる大がかりなものであり、治療費用もそれなりに高額になります。
手術の内容などによっても金額は異なりますが、3割負担の方の場合で、歯列矯正での自己負担額は約30万円以上、手術での自己負担額は約20万円以上がかかります。
ただし、保険適用の治療であれば高額療養費制度の対象となるため、所得によっては自己負担金額の一部が支給され、それぞれ自己負担額が10万円程度で収まる場合もあります。
まとめ

顎変形症は、症状が軽度である場合や、顎が発達段階にある幼少期であれば、歯列矯正の対応で改善できる可能性があります。一方で、症状が進行してしまった場合は大がかりな手術などが必要となる場合があり、治療に長い年月が必要になる可能性もあります。
手術を伴う顎変形症の治療は保険適用で受けることもできますので、治療が気になる方は、一度専門的な顎変形症の治療を取り扱う医療機関で相談してみてはいかがでしょうか。
参考文献
