顎関節症は日本人に多い慢性疾患で、開口や咀嚼時の痛み・雑音が日常生活を妨げます。その原因はひとつではなく、複数が組み合わさって発症することから、治療で完治させるのも簡単ではありません。
ここでは顎関節症になるとどこが痛いのか、発症する原因や治療法を解説します。顎の関節やその周りに違和感や痛みがある方は、このコラムを参考にしてみてください。
顎関節症を発症する原因
 顎関節は、頭の骨と顎の骨をつなぐ関節で、左右で1対あります。顎関節症はその顎関節に何らかの異常が生じる病気なので、歯周病やむし歯といった一般的な口腔疾患とは、原因が大きく異なる点に注意が必要です。
顎関節は、頭の骨と顎の骨をつなぐ関節で、左右で1対あります。顎関節症はその顎関節に何らかの異常が生じる病気なので、歯周病やむし歯といった一般的な口腔疾患とは、原因が大きく異なる点に注意が必要です。
歯ぎしりと食いしばり
顎関節症の原因として、第一に挙げられるのは歯ぎしりや食いしばりです。専門的にはブラキシズムと呼ばれるもので、歯や歯周組織、顎関節に過剰な負担を与えます。歯ぎしり(グラインディング)は、上下の歯をギリギリとこすり合わせる行為で、食いしばり(クレンチング)は、強く噛みしめることを指します。
顎の力はとても強く、食べものが介在せず歯と歯が直接接触する歯ぎしり・食いしばりでは、成人男性では100kg程度の圧力が発生するといわれています。このような負担が毎晩、数時間続くと、歯や顎関節を傷めてしまっても不思議ではありません。
そのため顎関節に痛みがあったり、お口を開け閉めするときに「カクカク」「ジャリジャリ」といった雑音が鳴ったりする場合は、まず歯ぎしりや食いしばりが習慣化していないか確認しましょう。
噛み合わせの不具合
歯ぎしりや食いしばりといった悪習癖がなかったとしても、噛み合わせに不具合があると、顎関節に過剰な負担がかかります。
具体的には、噛み合わせが深い過蓋咬合(かがいこうごう)や受け口、前歯部で噛むことが難しい開咬(かいこう)といった噛み合わせの異常を抱えていると、顎関節症になりやすいです。
猫背や首の前傾姿勢
正常な人の歯は、安静時に上下の歯列間で隙間が生じています。これを安静空隙(あんせいくうげき)といいます。スマートフォンやパソコンの画面を凝視して、猫背や前傾姿勢をとっていると下顎が不適切な位置へと誘導され、歯と歯が接触しやすくなったり、噛みしめたりすることで顎関節に大きな負担がかかります。
過度なストレスと緊張
学校や職場などで過度なストレスと緊張を強いられると、歯ぎしりや食いしばりが誘発されます。その結果、顎関節に過剰な力が加わって顎関節症を引き起こすこともあるのです。過度なストレスや緊張を受けていることは、自覚しにくく、気付いたときには顎の痛みが出ることも少なくありません。
顎関節症になるとどこが痛むのか
 顎関節は、頭の骨や顎の骨、顎の筋肉などさまざまな組織で構成されている構造なので、痛みの現れ方も多様です。
顎関節は、頭の骨や顎の骨、顎の筋肉などさまざまな組織で構成されている構造なので、痛みの現れ方も多様です。
顎
顎関節症では、食事や会話のときに顎が痛い、顎に違和感を覚えるといった症状が認められます。顎関節の周りに分布する筋肉が緊張していたり、顎関節に大きな負担がかかっていたりすることが原因です。
顎が痛いという症状は、親知らずのトラブルや外傷などでも生じうることから、診断は歯科医院で受ける必要があります。
耳の周り
顎関節は、上顎骨を構成する側頭骨(そくとうこつ)と下顎骨の関節突起と呼ばれる部分が接触するところで、耳の前に位置しています。そのため、顎関節症になると耳の前やその周囲に痛みを感じるのが一般的です。
お口を開けたときに雑音が鳴って、耳の前の部分にカクンッという異常な動きが見られたら、関節円板がズレている可能性が高いです。関節円板がズレることで強い痛みが生じることはほとんどありませんが、顎関節症の典型的な症状であることは知っておきましょう。
頬とこめかみ
顎関節症では、側頭筋(そくとうきん)、咬筋(こうきん)、外側翼突筋(がいそくよくとつきん)、内側翼突筋(ないそくよくとつきん)からなる咀嚼筋に大きな負担がかかり、筋肉のこりや痛みを引き起こすことがあります。
咬筋は、咀嚼機能の主体となる筋肉であり、主に顎の周りに分布していることから、顎関節症では顎が痛みますが、外側翼突筋と内側翼突筋は、頬の周囲に分布しているため、頬が痛いと感じる場合もあるのです。側頭筋に関しては、文字どおり頭の側面に分布しており、顎関節症ではこめかみの周辺に痛みを感じやすくなっています。
このように、ひと言で顎関節症といっても「どこが痛い」のかは一概に語ることが難しいです。上述した3つの部位もどれかひとつだけ症状が現れたり、すべてに痛みを感じたりするなど、状況によって大きく変わる点に注意しなければなりません。
顎関節症になるとどのようなときに痛むのか
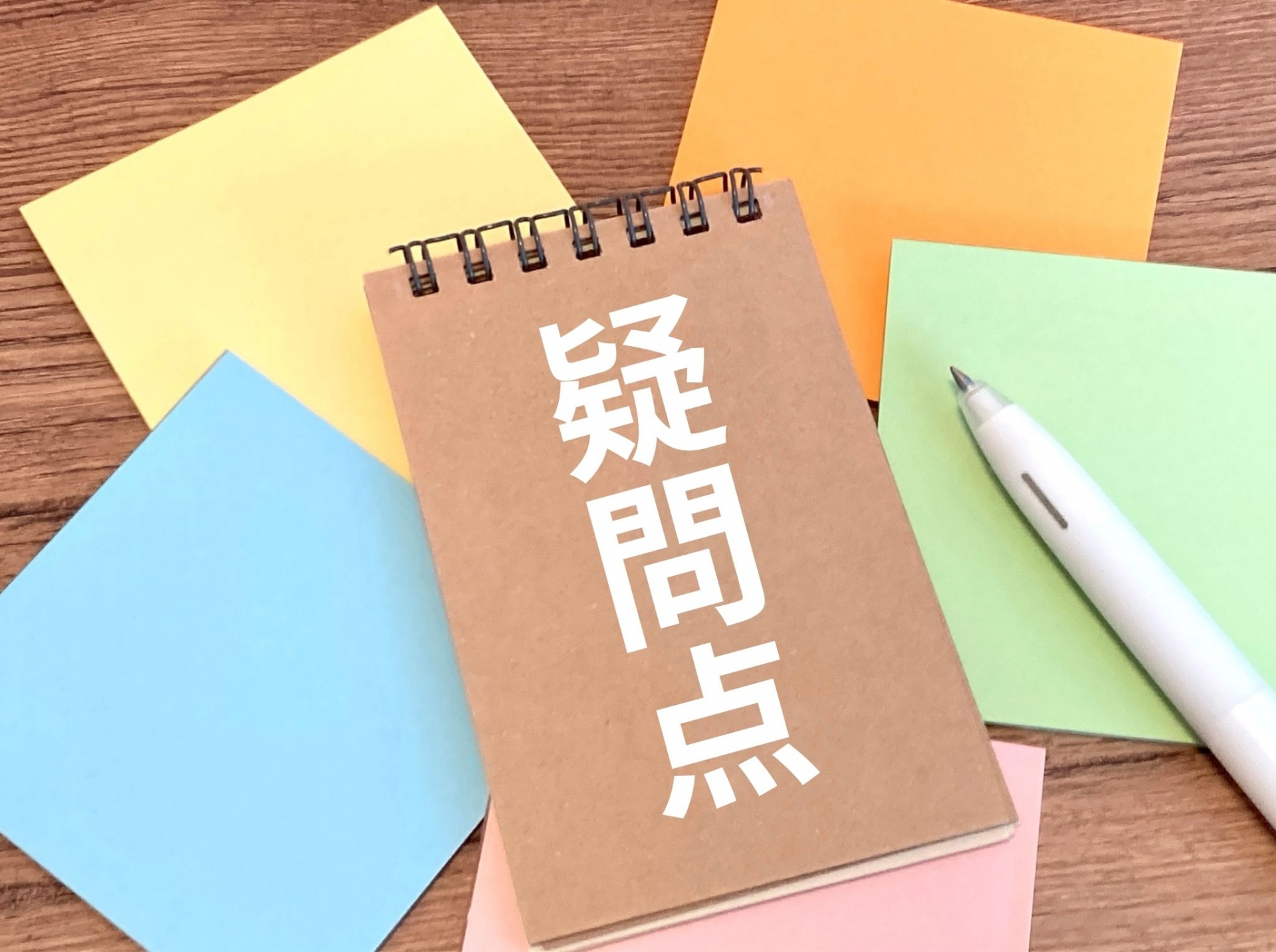 顎関節症を発症するとどのようなときに痛みを感じるのかについて解説します。顎関節症で痛みを感じるときは、以下のような場面です。
顎関節症を発症するとどのようなときに痛みを感じるのかについて解説します。顎関節症で痛みを感じるときは、以下のような場面です。
◎大きなあくびをしたとき
お口を大きく開けてあくびをすると、顎関節が大きく動きます。下顎骨の下顎頭(かがくとう)が回転して前方へと走り出します。顎関節症では、顎関節のクッションの役割を果たす関節円板がズレたり、骨の形や筋肉の動きに異常があったりするため、お口を大きく開けると、顎の痛みが強くなりやすいのです。そうしたことから顎関節症の患者さんは、自然とあくびを大きくするのを避けるようになります。
◎食事をしているとき
顎関節症で痛みが生じやすいのは、食事をしているときです。咀嚼運動は、下顎骨が大きく動くだけでなく、噛んだときの圧力が顎関節へと伝わることから、顎に強い痛みが生じやすくなっています。
特に硬い食べものや弾力性の高い食べものをしっかり噛もうとすると、顎の痛みが強くなるため、顎関節症の患者さんはあまり噛まずに飲み込めるものを積極的に選ぶようになるのです。それ自体は顎関節への負担を減らすうえでよい取り組みといえますが、やわらかいものばかりの食生活では、唾液の分泌量が減る、咀嚼筋が衰える、食事の栄養バランスが悪くなるなどのデメリットを伴うため、顎関節症そのものを改善することが大切です。
顎関節症の痛みに対する治療方法
 顎関節症が進行すると、安静にしているだけでは痛みを緩和できなくなります。以下に挙げるような積極的な治療が必要となります。
顎関節症が進行すると、安静にしているだけでは痛みを緩和できなくなります。以下に挙げるような積極的な治療が必要となります。
スプリント装着療法
顎関節症における一般的な治療方法は、スプリント療法です。スプリントというマウスピース型の治療装置を夜間に装着して、歯や顎関節への負担を軽減します。
顎関節症の主な原因は、歯ぎしりや食いしばりによる刺激なので、スプリントで歯と歯が強く接触するのを防げれば顎関節症の痛みも和らぎます。スプリント療法では、下顎を正常な位置へと誘導する効果も期待できることから、治療を続けていくなかで歯ぎしりや食いしばりが起こりにくくなり、顎関節症の原因を取り除ける可能性もあるのです。
スプリント療法だけで顎関節症を完治させることは容易ではありませんが、現状では有効な治療法のひとつであることに間違いありません。
温熱療法と運動療法
顎関節症の痛みは、お口周りの筋肉のこりが原因となっている場合も少なくありません。そこで有用なのが咬筋や側頭筋のこりを和らげ、血流をよくする温熱療法や運動療法です。これらは顎関節症への対症療法であり、根本的な原因を取り除くことはできませんが、専門家による施術を受けることで、顎関節の痛みを改善しやすくなるでしょう。
ちなみに、咬筋や側頭筋のこりをほぐす目的で自己流のマッサージをすることは、顎関節症の症状をかえって悪化させるリスクを伴うため、まずは専門家による施術を受けることが推奨されます。そのなかで自宅でもできるマッサージ法があれば、専門家の指導を受けながら、積極的に実践していきましょう。
消炎鎮痛薬の服用
顎関節症の痛みを即時的に緩和する方法としては、消炎鎮痛薬の服用が有効です。消炎鎮痛薬は、炎症反応と痛みを抑えることができる薬剤なので、顎関節症に伴う症状にはすぐに効果が現れます。
消炎鎮痛剤を使った薬物療法も温熱療法や運動療法と同じく、対症療法でしかないことから、顎関節症の根本的な原因は取り除けません。また、消炎鎮痛剤には胃腸障害や腎障害、アレルギーなどの副作用が起こるリスクも伴うため、日常的に服用するのは推奨できません。顎関節症で我慢できない痛みが生じたときのみ、一時的に使用するのが望ましいです。
顎関節腔洗浄療法
顎関節腔洗浄療法(がくかんせつくうせんじょうりょうほう)とは、顎関節症における外科的な治療法のひとつです。顎関節にある顎関節腔というスペースに2本の注射針を刺して、内部に貯留した体液などを灌流洗浄します。
顎関節腔洗浄療法は皮膚をメスで切開することはなく、生理食塩水で30分洗浄するだけなので、術後に痛みや腫れが大きく出ることもほとんどありません。顎関節腔内の洗浄が終わったら、ヒアルロン酸やステロイドを注入して処置は完了です。
日常生活でできる顎関節症の予防策
 顎関節症を予防する方法について解説します。顎関節症は、一度発症するとなかなか治りにくい病気ですが、症状が強く現れる時期もあれば、ほとんど気にならなくなる時期もあります。後者に関しては、日常生活で以下に挙げる方法を実践することで、症状の出現を予防しやすくなるため、積極的に取り組んでみてください。
顎関節症を予防する方法について解説します。顎関節症は、一度発症するとなかなか治りにくい病気ですが、症状が強く現れる時期もあれば、ほとんど気にならなくなる時期もあります。後者に関しては、日常生活で以下に挙げる方法を実践することで、症状の出現を予防しやすくなるため、積極的に取り組んでみてください。
正しい姿勢を保つ
顎関節症は悪い姿勢によって症状が誘発されることがあります。スマートフォンやパソコン、テレビの画面を見ているときの姿勢には十分注意をしましょう。
基本的には背筋を真っすぐ伸ばし、顎が前方へと突出しないよう意識することが大切です。気付いたら猫背になってしまっているという方は、スマートフォンやタブレット、テレビの画面を見る時間を自発的に減らすとよいでしょう。
特にスマートフォンの小さな画面を1日に長時間のぞき込んでいると、猫背やストレートネック、巻き肩などの姿勢不良が引き起こされて、顎関節症以外の症状も誘発されます。
顎の筋肉をストレッチする
顎の筋肉も手足の筋肉と同じように、ストレッチすることで血流がよくなります。歯ぎしりや食いしばりによるこりも改善され、顎関節症の予防に役立ちますので、日々の生活の中で顎の筋肉をストレッチする時間を設けるとよいでしょう。顎の筋肉の正しいストレッチ方法は、歯科医院で学んでください。
やわらかい食べ物を小さく切って食べる
過去に顎関節症を発症した方や今は顎関節症の症状が落ち着いているという方は、硬い食材は控えめにしましょう。具体的には、ナッツ類やおせんべい、フランスパンなどは顎関節に大きな負担をかけることから、顎関節症を予防するという観点では好ましくないです。
硬くない食材でも顎関節への影響を考慮して、小さく切ってひと口大にしたり、煮込んでやわらかくしたりした方がよいといえます。ただし、お粥やリゾット、スムージーなど、あまり噛まずに飲み込めるものばかり食べていると、顎の力が弱まってしまうことから、適度に配慮することが大切です。
定期的に歯科検診を受ける
顎関節症をしっかりと予防したいという方は、3〜6ヶ月に1回の頻度で歯科検診を受けましょう。歯科検診ではむし歯や歯周病の有無だけでなく、噛み合わせの異常や歯ぎしりによる影響なども早期に発見でき、顎関節症の予防につなげることができます。
また、歯科検診で定期的に通院していれば、顎関節の気になる症状や不安に感じている生活習慣などについても歯科医師に相談しやすくなることでしょう。
まとめ
今回は、「顎関節症になるとどこが痛い?」という疑問に答え、顎関節症になる原因や治療法、予防方法についても解説しました。顎関節症になると顎や耳の周り、頬とこめかみなどが痛くなりますが、痛みの範囲や痛みが出るタイミングには個人差がある点に注意が必要です。また、顎関節症になる原因も多岐にわたることから、顎や耳の周りが痛いと感じたら、自己診断せずにまずは歯科医師を受診しましょう。歯科医院ではさまざまな方法で顎関節症を治療することができます。
参考文献
