口腔粘膜疾患は、お口のなかの健康に大きな影響を与える問題で、口内炎や口腔がんなどさまざまな疾患が含まれます。これらの疾患は似たような症状を示すことがあり、自己判断では見分けがつかないこともあります。
本記事では口腔粘膜疾患の見分け方について以下の点を中心にご紹介します。
- 口腔粘膜疾患とは
- 口腔粘膜疾患の種類
- 口腔粘膜疾患の治療
口腔粘膜疾患の見分け方について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
口腔粘膜疾患とは

口腔粘膜疾患は、口唇、舌、歯肉、頬粘膜、口蓋、口底など、お口のなかの粘膜部分にさまざまな症状が現れる疾患です。これには、びらん、潰瘍、腫瘤、水疱などが含まれます。
口腔内は唾液によって保護され湿潤状態が保たれていますが、歯や食べ物、温度などの刺激を受けやすいため、局所的な安静を保つことが難しく、症状が変化しやすいのが特徴です。
また、口腔内には常在菌が多く存在し、感染による影響を受けやすい環境でもあります。そのため、口腔粘膜疾患は多岐にわたる症状を引き起こし、病変が刺激によって二次的に修飾されることがあるため、診断や原因の特定が難しいことが多いようです。
口腔粘膜に現れる症状には、色調や表面の性状が変化することがあり、代表的な色の変化としては赤、白、黒、黄、紫などが挙げられます。
これらの変化は口腔粘膜疾患に共通する症状であり、疾患によっては自覚症状がないこともあるため、診断や治療に時間がかかることがあるようです。
口腔粘膜疾患の種類

口腔粘膜疾患の種類はどのようなものがあるのでしょうか。以下で詳しく解説します。
白板症
白板症は、主に頬粘膜や舌、歯肉などの口腔粘膜に現れる白い病変で、こすっても簡単には剥がれない特徴があります。特に舌にできた場合、悪性化する可能性が高いため、前がん病変(口腔潜在的悪性疾患)とされています。
この病変は、びらん(粘膜の浅い欠損)を伴うこともあり、接触痛や食べ物のしみる感じが生じることがあります。
白板症の原因は、喫煙やアルコールの摂取、義歯などの慢性的な機械的刺激、ビタミンAやBの不足、加齢や体質などが挙げられます。これらの要因が重なることで、白板症のリスクが高まるとされています。
治療法には、ビタミンAの投与や禁煙がおすすめな場合もありますが、しこりや潰瘍を伴う場合には初期がんが疑われるため、早急に生検を行い、組織検査を実施することが重要です。
また、白板症が厚みを持ち、隆起したり、びらんや潰瘍を伴ったりする場合、悪性化するリスクが高いため、切除を考慮します。
さらに、白板症は長期間経過して悪性化することもあるため、定期的な経過観察が求められます。
白板症は自覚症状がないことがあるため、高齢者に多くみられ、50〜70代の男性に発症しやすい傾向があります。
発見が早ければ治療も可能とされていますが、早期発見が難しいこともあるため、定期的な口腔内チェックが重要です。
紅板症
紅板症は、主に舌や歯肉、その他の口腔粘膜に現れる病変で、鮮やかな赤色を呈し、ビロードのような質感があります。病変の表面は平滑で、境界がはっきりしていることが特徴です。
初期の症状には、刺激痛が感じられることがあり、50歳代以上の高齢者にみられることが多いとされ、全体の80%がこの年齢層に該当するようです。
紅板症は、悪性化のリスクが高く、約50%の症例が悪性化するといわれています。このため、早期に発見し、治療を行うことが重要です。
治療法としては、外科的に切除することが推奨されており、切除後も悪性化を防ぐための経過観察が必要です。
自己免疫性水疱症(天疱瘡・類天疱瘡など)
原因ははっきりしていませんが、お口のなかの粘膜や皮膚に水ぶくれが現れる病気です。口腔内で水ぶくれができても、すぐに破れてしまうことがあり、これがびらんや潰瘍となり、痛みや出血を伴います。
そのため、食べ物を食べるのが辛かったり、飲み込みにくくなったり、歯磨きがしにくくなることがあります。
また、強い口臭を伴うこともあります。
自己免疫性水疱症は主に皮膚科での診断と治療が行われますが、口腔粘膜に症状が現れることがあるため、特に歯茎に症状が現れると歯周病との区別が難しくなります。
この場合、歯科医院で歯周病の治療を行っても症状が改善しないことがあるため、この病気を疑うことがあります。
自己免疫性水疱症(例えば、天疱瘡や類天疱瘡など)が疑われる場合、速やかに専門医療機関への紹介が行われる場合があります。
また、治療中に口腔ケアが普段どおりにできない場合もありますが、患者さんが通院できれば、口腔ケアの方法についてアドバイスやサポートを受けられます。
扁平苔癬(へんぺいたいせん)
皮膚や粘膜に現れる角化性の病変で、炎症を伴い、治療が難しいことが特徴です。
口腔内では主に頬粘膜に見られますが、舌や口唇にも発生することがあります。白い角化した粘膜がレース状に広がり、周囲に発赤が見られることが特徴的です。しばしば、びらんや潰瘍を伴い、接触痛や食べ物が染みることがあります。
まれに、がんに進行することもあります。
原因としては、アレルギー(特に歯科用金属によるもの)や遺伝的な素因、自己免疫疾患、ストレスなどの精神的な要因、さらに代謝障害が関与していると考えられていますが、正確な原因は明らかになっていないようです。
口腔乾燥症
お口が乾くことは、水分摂取が不足していたり、急激に多量の水分が失われたりする場合に起こります。例えば、激しい運動による多量の発汗などが原因です。
しかし、慢性的にお口が乾く場合は、全身の疾患や重大な障害が考えられることがあります。
例えば、腫瘍による嚥下困難や糖尿病による多尿など、脱水症状が口渇を引き起こす原因となることがあります。
また、抗ヒスタミン薬や制酸薬、降圧薬、向精神薬の服用も唾液の分泌を減少させることがあります。
さらに、口腔がんや咽頭がんの放射線治療後にも顕著な唾液分泌の障害が見られることがあります。
鼻づまりによる口呼吸や、義歯が唾液分泌を抑制する場合もあります。
帯状疱疹
子どもの頃にかかった水痘(みずぼうそう)のウイルス(水痘帯状疱疹ウイルス)が神経のなかに潜んでおり、体調が崩れると再び活性化して発症します。
発症すると、神経が支配する範囲に沿って発疹が現れ、顔面の三叉神経領域に多くみられます。
発疹は広範囲にわたり帯状に発赤や小水疱(すいほう、水ぶくれ)ができますが、発生するのは体の右または左側の片側だけで、全身には広がりません。
強い痛みを伴い、重症化することもあるため、注意が必要です。
一部の口内炎
一部の口内炎も、口腔粘膜疾患にあたります。具体的には以下のとおりです。
アフタ性口内炎・再発性アフタ
アフタは直径数ミリの円形の浅い潰瘍で、潰瘍の表面には灰白色や黄白色の偽膜が覆い、周囲が赤くなります。食べ物や歯ブラシが少し触れただけでも強い痛みを感じ、刺激の強い食べ物や熱いもの、塩辛いものがしみることがあります。
アフタは特別な治療をしなくても1〜2週間程で自然に治癒することが多いとされていますが、再発を繰り返す場合は「再発性アフタ」と呼ばれます。
慢性再発性アフタは、ベーチェット病の一症状として現れることもあります。
アフタの原因ははっきりしていませんが、機械的な刺激、遺伝的な要因、極度の疲労やストレス、栄養の偏りなど、さまざまな要因が関係していると考えられています。
ベーチェット病では、遺伝的な素因が関与しているとされています。
口腔カンジダ症(カンジダ性口内炎)
カンジダ・アルビカンスという真菌(かび)によって引き起こされる口腔内の感染症で、急性型と慢性型があります。
口腔内の粘膜に痛みや味覚の異常が現れることもあります。
急性型の偽膜性カンジダ症では、粘膜の表面に灰白色または乳白色の点状、線状、斑紋状の白苔が現れます。この白苔はガーゼで簡単に拭き取れ、剥がした後の粘膜は発赤やびらんを伴います。
一方、白苔がみられない場合は萎縮性や紅斑性カンジダ症となり、舌の乳頭の萎縮や粘膜の赤みが特徴です。
これらの状態は、偽膜性カンジダ症よりも痛みが強く、ヒリヒリした感覚が感じられます。
また、口角部に赤み、びらん、亀裂が生じる口角炎もカンジダが原因で起こることがよくあるそうです。
病変が慢性化した肥厚性カンジダ症では、白苔が剥がれにくくなり、上皮が肥厚します。
ヘルペス性口内炎
ヘルペス性口内炎は、疱疹性歯肉口内炎(ほうしんせいしにくこうないえん)とも呼ばれます。通常は無症状で進行し、不顕性感染(症状が現れない感染)としてみられることが多いようです。
多くは小児にみられますが、近年では核家族化の影響もあり、大人にも発症することがあります。
発熱や倦怠感(だるさ)が全身的に現れることがあり、口腔内には多数の口内炎が発生し、粘膜全体が赤くなります。
特に歯肉においては発赤、腫れ、びらんが見られ、口腔内が不潔になり、口臭が強くなります。
手足口病
コクサッキーA16型やエンテロウイルス71型による感染です。
口腔内に小さな水疱ができ、これが破れてアフタ様の病変を引き起こすとともに、手足にも小さな水疱が現れることが特徴的なウイルス性疾患です。
ヘルパンギーナ
エンテロウイルス属、特にA群コクサッキーウイルスによる感染で、軟口蓋から口峡部にかけて発赤と多数の小水疱が現れます。
これらの水疱は破れて小さなアフタ状の病変を形成します。
ヘルペス性口内炎が口腔の前方に症状を示すのに対して、こちらは口腔後方と咽頭に発症することが特徴です。
この疾患は夏に流行しやすく、小児によくみられますが、稀に大人にも発症することがあります。
似ている口腔粘膜疾患の見分け方
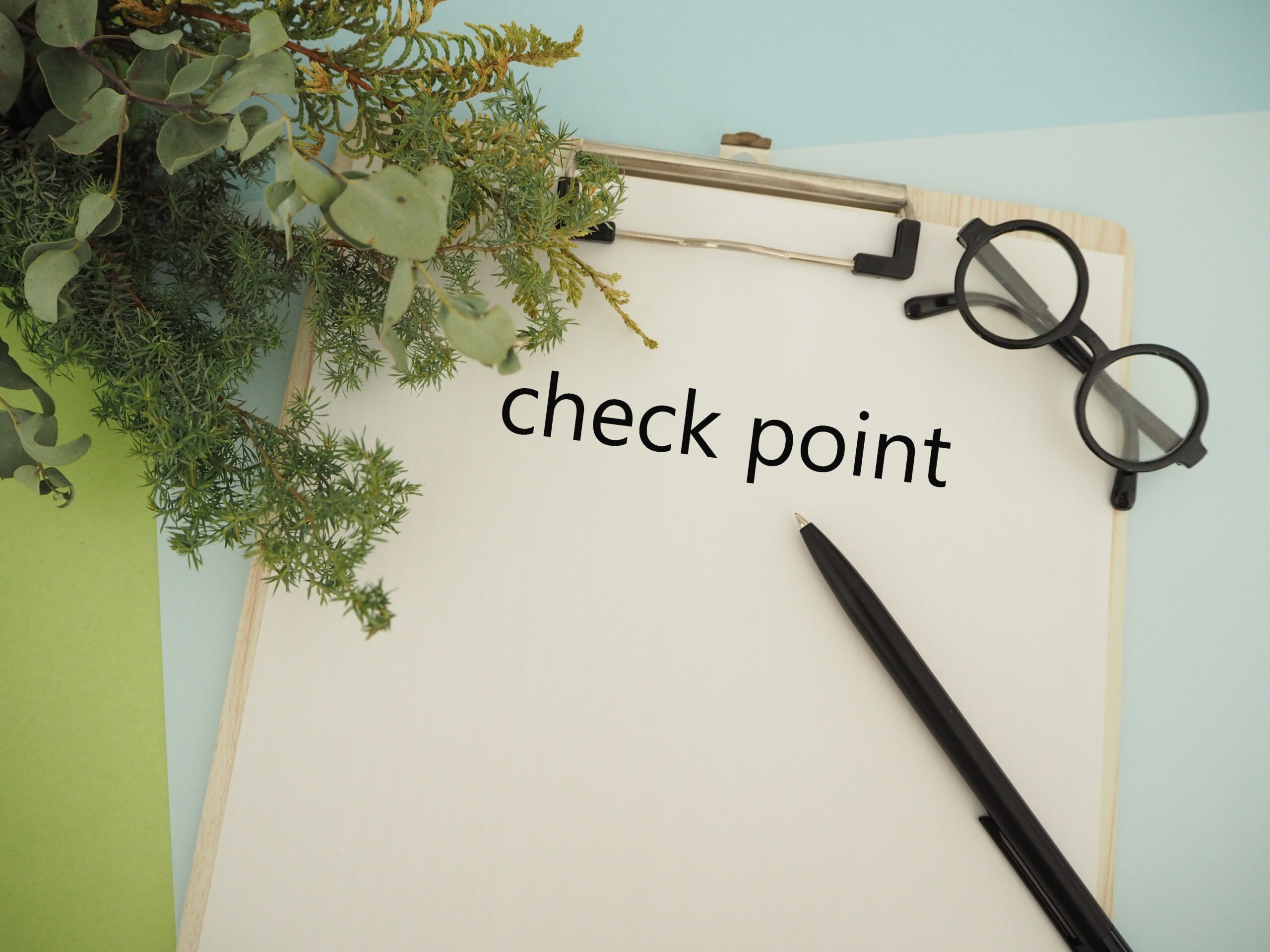
似ている口腔粘膜疾患の見分け方について、以下で詳しく解説します。
白板症とカンジダ性口内炎
粘膜が白く変化し、ときにはただれを伴うことがあり、カンジダ性口内炎に似た症状が現れることがあります。
白板症とカンジダ性口内炎との違いは、カンジダ性の場合、白い膜がこするだけで簡単に剥がれますが、白板症ではこすっても膜が剥がれず、むしろ厚みを増し硬くなっていきます。
白板症は必ずしも痛みを伴うわけではないため、症状が現れても放置されがちですが、約5~10%の確率で悪性化(がん化)する可能性があるため、注意が必要です。
紅板症と口内炎など
口腔粘膜が鮮やかな赤色のビロード状になり、境界がはっきりしています。
これに似た症状として、白板症や口腔カンジダ症の紅斑型、扁平苔癬(かゆみを伴う発疹が現れる疾患)、口内炎などがあります。
なかなか治らない口内炎は注意が必要
市販薬を使用して1~2日程で症状が悪化する場合や、5~6日程使用しても改善がみられない場合は、使用した薬を持参のうえ、受診を検討しましょう。
また、痛みがなくても、約2週間以上口内炎のような症状が続く場合、口内炎とは異なる病気の可能性も考えられるため、早めの受診をおすすめします。
口腔粘膜疾患と口腔がん・口内炎

口腔粘膜疾患と口腔がん・口内炎について以下で詳しく解説します。
口腔がんとは
口腔がんは、お口のなかに発生する悪性腫瘍のことを指します。
口腔内では、舌、上下の歯肉(歯茎)、頬粘膜(頬の内側)、硬口蓋(お口の上部分の硬い部分)、口腔底(舌と下の歯肉の間)に発生することがあります。
また、唇に発生するがん(口唇がん)もあります。
口腔がんの約90%は、粘膜組織から発生する扁平上皮がんというタイプのがんです。
口腔がんの前触れとなる口腔粘膜疾患
歯肉や舌、頬の内側などの粘膜が白く変色し、こすってもその白い部分が取れない状態が約1ヶ月以上続く場合、「白板症」という病気の可能性があります。
白板症は将来的にがんに進行するリスクがあるため、早期に発見し、長期的に経過を観察することが重要です。
少しでも異常を感じた場合は、早めに歯科医院で相談することをおすすめします。
口腔がんと口内炎の見分け方
口内炎と口腔がんの大きな違いは、自然に治るかどうかという点です。
口内炎は時間が経てば治りますが、口腔がんは自然に回復することはありません。
もし、約2週間以上口内炎が改善しない場合は、歯科医院や口腔外科での受診を検討することをおすすめします。
口腔粘膜疾患の治療
アフタ性潰瘍、口腔扁平苔癬、または水疱が破れて生じたびらんや潰瘍に対しては、主に局所的な副腎皮質ステロイド薬(軟膏やスプレー剤)が使用されます。
痛みが強い場合は、麻酔成分を含むうがい薬を併用することもあります。
口腔粘膜疾患では、二次感染を予防するために口腔内を清潔に保つことが大切です。
口腔カンジダ症やヘルペス性口内炎には、抗真菌薬や抗ウイルス薬による治療が行われます。
抗真菌薬は内服やうがいなどさまざまな方法で使用され、患者さんの口腔内の状態に応じて使用量や方法を調整します。
口腔カンジダ症では、口腔乾燥症が同時にみられることがあるため、両方の治療を並行して行うことが必要です。
また、口腔乾燥症の治療には唾液腺刺激療法、マッサージによる唾液腺の刺激、保湿ジェルやスプレー、人工唾液、保湿装置などを使用し、症状を緩和する対症療法が中心となります。
シュガーレスガムやレモンなど、唾液分泌を助ける食品を摂取したり、人工唾液で補充したりするのもおすすめです。
さらに、貧血が原因で舌炎が疑われる場合は、血液内科を受診し、鉄剤やビタミンB12の内服治療を始めることがあります。
まとめ

ここまで口腔粘膜疾患の見分け方についてお伝えしてきました。
口腔粘膜疾患の見分け方についての要点をまとめると以下のとおりです。
- 口腔粘膜疾患とは、口唇、舌、歯肉、頬粘膜、口蓋、口底など、お口のなかの粘膜部分にさまざまな症状が現れる疾患を指す。これには、びらん、潰瘍、腫瘤、水疱などが含まれる。口腔内は唾液によって保護され湿潤状態が保たれているが、歯や食べ物、温度などの刺激を受けやすいため、局所的な安静を保つことが難しく、症状が変化しやすいのが特徴
- 口腔粘膜疾患の種類は、頬粘膜や舌、歯肉などの口腔粘膜に現れる白い病変「白板症」や舌や歯肉、その他の口腔粘膜に現れる病変「紅板症」などが挙げられる
- 口腔粘膜疾患の治療は、アフタ性潰瘍、口腔扁平苔癬、または水疱が破れて生じたびらんや潰瘍に対しては、主に局所的な副腎皮質ステロイド薬(軟膏やスプレー剤)が使用される
口腔粘膜疾患は多岐にわたり、見た目が似ているために自己判断が難しいことがあります。しかし、早期に適切な診断を受けることで、治療の選択肢が広がり、予後を改善することができます。
口内炎や口腔がんなどは症状が進行する前に対処することが重要です。
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
